情報セキュリティ
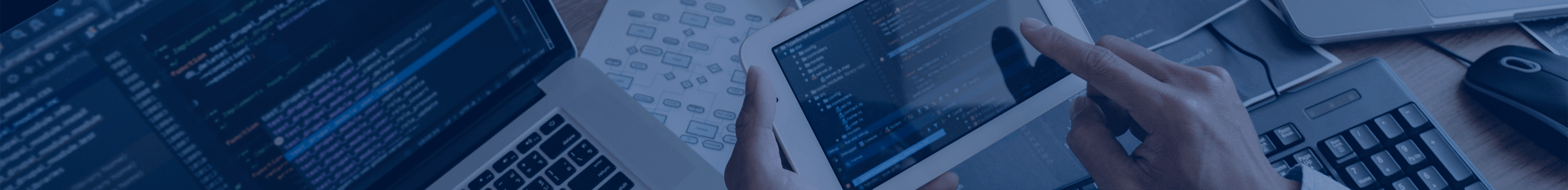
J-CRAT 標的型サイバー攻撃特別相談窓口
最終更新日:2025年4月1日
独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター
Topics :
IPAでは企業/組織向けに、セキュリティインシデントに関する相談を受け付ける窓口を2025年4月1日(火曜日)に開設いたしました。今後、標的型サイバー攻撃(APT)に関する相談・情報提供につきましては「企業/組織向けサイバーセキュリティ相談窓口」までお願いいたします。
IPAでは、2008年9月から標的型攻撃メールの相談窓口として「不審メール110番」(2010年10月から「情報セキュリティ安心相談窓口」に統合)を設置し、2011年10月には、おもに国家支援型と推定される標的型サイバー攻撃(APT)を受けた際に、専門的知見を有する相談員が対応する「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」を設置し、相談を受け付けています。また、2014年7月には、経済産業省の協力のもと、標的型サイバー攻撃を受けている組織の対応を支援するサイバーレスキュー隊(J-CRAT)を発足させています。
標的型サイバー攻撃では、事象の発生や結果を集約し分析することで、個々の攻撃のみからでは分からない攻撃手口や傾向をとらえていくことが必要です。特に、標的型メール攻撃については限られた対象にのみ行われています。そのため、みなさまからの情報提供により、その手口や実態を把握することが最重要となります。標的型攻撃メールを受け取った場合やネットワーク貫通型攻撃などの標的型攻撃に曝された際は、ぜひ「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」への情報提供にご協力ください。いただいた知見は、必用に応じわが国のサイバー状況把握や、官民連携における情報共有などに利活用させていただくことがございます。
国家支援型サイバー攻撃に関わる情報提供
国家支援型サイバー攻撃に関わる被害や未遂事例(例えば標的型攻撃メールと思われるメールを受信した場合)がございましたら、「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」に情報をご提供ください(バラマキ型メールやフィッシングメール、ビジネス詐欺メールなど判断できる場合は原則情報提供不要です)。
その際、以下のような情報を添えて、ご連絡をお願いいたします。
- < 例 (書式に指定はありません) >
-
- 経緯、被害状況(未遂の場合含む)
- メールの件名、添付ファイル名、本文
- 送信者および受信者の組織名
いただいた情報提供につきまして、IPAでの追加の調査が必要であると判断した際などは、折り返しご連絡する場合がございます(ご相談の内容に応じ、異なる部門へ引き継がせていただく場合もございます)。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、標的型攻撃メールか判断のつかない場合は、「標的型攻撃メールの見分け方」をご参照ください。
標的型サイバー攻撃特別相談窓口のご案内
標的型サイバー攻撃特別相談窓口の連絡先は以下の通りです。
- E-mail:
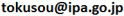
-
標的型サイバー攻撃(APT)以外の一般的な情報セキュリティ(主にウイルスや不正アクセス)に関する企業/組織向けの相談は「企業/組織向けサイバーセキュリティ相談窓口」、個人向けの相談は「情報セキュリティ安心相談窓口」、分類が困難なウイルスや不正アクセスに関する届出は「コンピュータウイルス・不正アクセスに関する届出窓口」にて受け付けています。
また、ご相談の内容に応じまして、ご相談いただいた窓口とは異なる部門からの返信となる場合や、複数の部門からの連絡となる場合がございます。
-
調査にあたり、追加情報が必要となる場合がございます。その際、別途情報提供専用のメールアドレスを連絡いたしますので、ご対応をお願いいたします。
-
このメールアドレスへの特定電子メール法に違反するメール(いわゆる迷惑メール)の送信はお控えください。
-
迷惑メールに関する設定などにより、IPAからのメールを受信できない場合があります。ご相談の際は、上記「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」のメールアドレスをはじめとした「ipa.go.jp」ドメインからのメールを受信できるような設定をお願いいたします。なお、宛先エラーなどの理由で当方からのメール返信が失敗した場合、再度のご連絡はいたしませんので、予めご了承ください。
政府連携
- サイバーセキュリティ分野における防衛省・経済産業省・IPAによる包括的な連携協定を締結
- 警察庁・NISCによるサイバー攻撃の注意喚起
