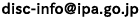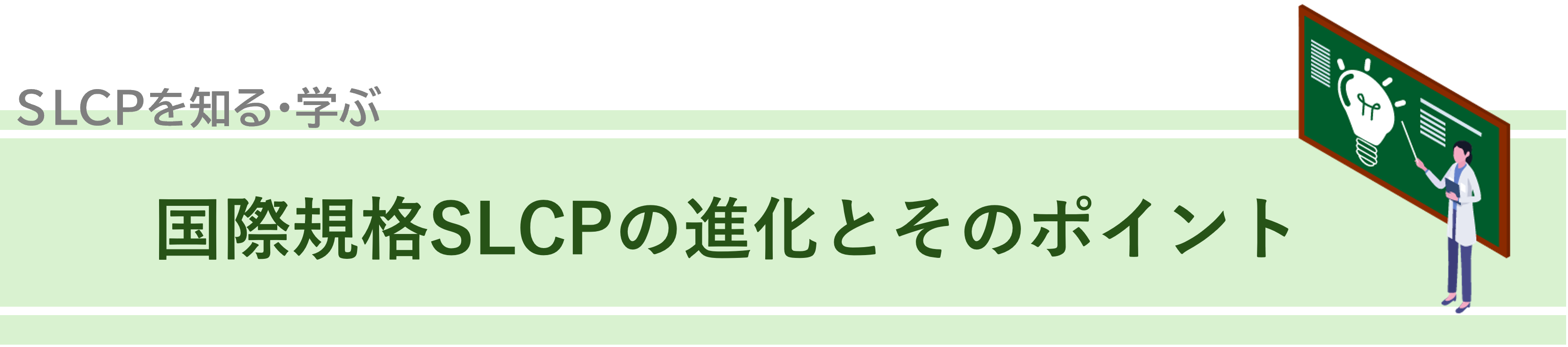社会・産業のデジタル変革
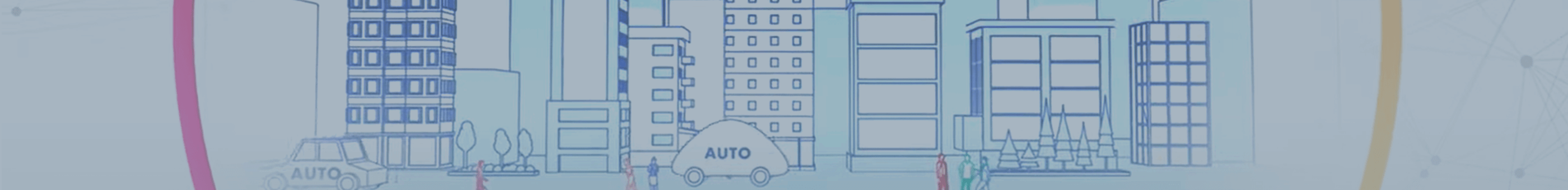
国際規格SLCPの進化とそのポイント
公開日:2025年9月30日
独立行政法人情報処理推進機構
デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部
ソフトウェアエンジニアリンググループ
概要
国際規格SLCP(System and Software Life Cycle Processes(ISO/IEC/IEEE 15288,12207))は、2015年以降の改訂において大きな変更が行われました。
本ページでは、国際規格SLCPの進化のポイントを紹介します。
国際規格SLCPの重要性については下記のページを参照してください。
SLCPとは
SLCPはISO/IEC/IEEEで策定・改訂されてきた国際規格群に基づく枠組みであり、システムやソフトウェア開発において、企画から設計、運用、廃棄に至るライフサイクルの各プロセスで組織やプロジェクトがどのような作業や活動を行うのかを記述しています。
SLCPには、「システムライフサイクルプロセス(ISO/IEC/IEEE 15288)」と「ソフトウェアライフサイクルプロセス(ISO/IEC/IEEE 12207)」の2種類があります。前者は、自動車、航空宇宙、防衛、家電などハードウェアとソフトウェアが一体となって機能する製品のシステムを対象に、後者は、製品・システムの構成要素であるソフトウェアや業務システム(財務、人事、販売管理など)、ITサービス、アプリケーションのように「ソフトウェアが主体」のシステムを対象に記述されています。
2015年以降のSLCPの進化とそのポイント
2015年以降に進化したSLCPの主なポイントを3点挙げます。
- (1)システムとソフトウェア二つのプロセスの調和(同一化)
-
両SLCPは、当初よりシステムとソフトウェアで別々に規格化されていましたが、ソフトウェアはシステムの構成要素であるという考えのもとで、両SLCPは併用して利用されていました。しかし、用語やプロセスの整合が不十分であったため、使い易くするための調和(整合)作業が2008年版から始まり、それぞれの2015年版と2017年版で一貫性のあるプロセス構成が出来上がり調和(同一化)されました。
- (2)要求の捉え方の変化
-
2008年版以前は、要求を「上流工程の入力情報」として扱う色合いが強かったのですが、2015年版以降は、「ビジネスや組織の役割を分析するプロセス」が追加され、要求は、ビジネス戦略から始まるシステムライフサイクル全体で継続的に検討・管理されるべきものとして捉えるように変化しています。
- (3)意思決定のためのシステム分析プロセスの追加
-
2015年版以降、「システム分析プロセス」が追加され、ライフサイクル全体を通して意思決定のための正確な情報が必要な場合に実施されます。
共通フレーム2013との関係
日本国内で、ソフトウェア開発のバイブルとして活用されている「共通フレーム2013」は、国際規格ソフトウェアライフサイクルプロセスISO/IEC12207 : 2008(JIS X 0160 : 2012)を包含し、かつ日本のソフトウェア産業界で必要とされるプロセスや作業項目を追加しています。
資料ダウンロード
詳細は次の「国際規格SLCPの進化とそのポイント」を参照してください。
お問い合わせ先
IPA デジタル基盤センター
デジタルエンジニアリング部 ソフトウェアエンジニアリンググループ
-
E-mail