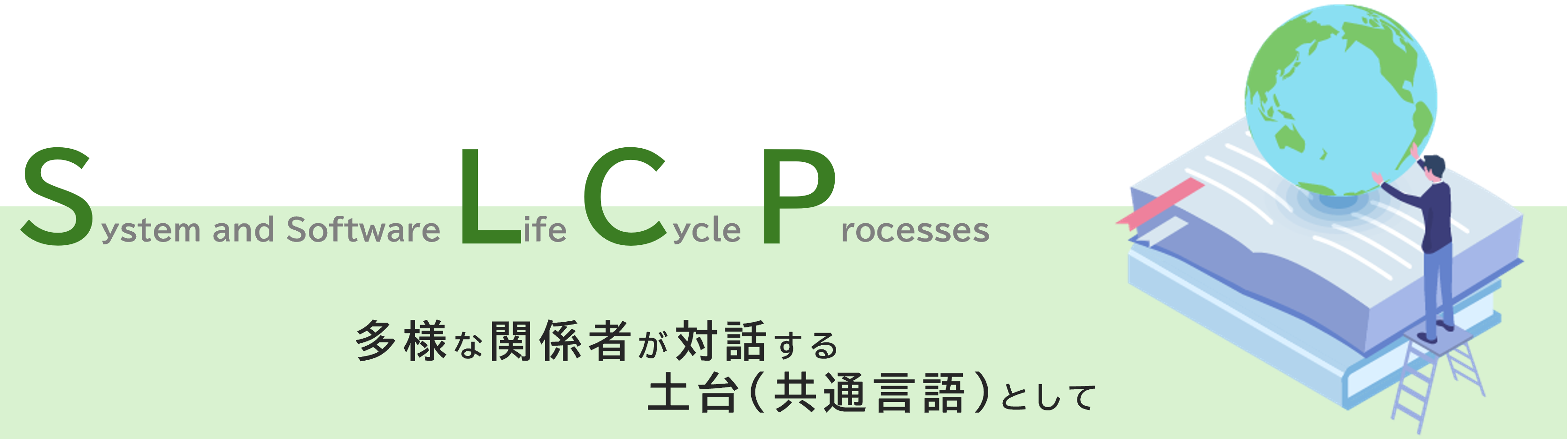社会・産業のデジタル変革
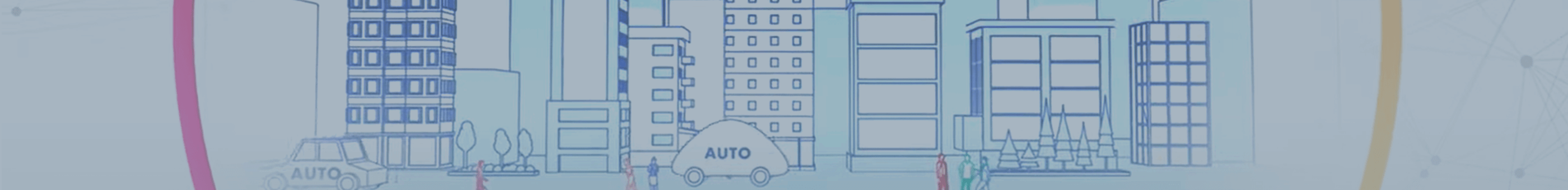
国際規格SLCP:システム&ソフトウェアのライフサイクル・プロセス
概要
本ページでは、システムやソフトウェアを企画・開発・運用・廃棄する一連の過程(ライフサイクル)を共通の言葉で整える枠組みである国際規格SLCP (System and Software Life Cycle Processes、(ISO/IEC/IEEE 15288,12207))の重要性と、その活用に有用な情報を提供します。
国際規格SLCPとは
生成AIをはじめとするデジタル技術の発展が加速し、産業と社会は大きな転換点を迎えています。SDV(Software-Defined Vehicle)に代表されるように、ソフトウェアで制御される多様なシステムが新しい価値の創出を先導する時代になってきました。今後もこの潮流は強まっていき、複数のシステムが接続・連携する基盤を活用し、社会課題の解決と経済発展を同時に追求していくことになります。
システムやソフトウェアを企画・開発・運用・廃棄する一連の過程(ライフサイクル)には、事業部門、情報システム部門、現場の利用者、調達・法務、監査、そして外部のパートナー企業など多様な関係者が関わります。そのような人達が共通の土台を持たずに議論すると合意に時間がかかり、しばしば作り直しや契約トラブルが発生します。国際規格は多様な関係者が対話する土台(共通言語)として活用できます。
システムとソフトウェアのライフサイクルについては、30年以上にわたり各国の有識者が参画して、ウォーターフォール/アジャイル/ハイブリッド開発等の特定の手法に依存しない国際規格の整備が進められてきました。ISO/IEC/IEEE 15288 および ISO/IEC/IEEE 12207(総称して System and Software Life Cycle Processes:SLCP)は、時代の変化を踏まえて改訂が重ねられています。グローバルな競争・協調を見据えるうえでも、国際規格を踏まえて共通の前提で議論し、ソフトウェアの特性を生かして社会的な便益をもたらすシステムを構築・運用することが重要です。
SLCPの特徴・メリット
- 共通言語になる
- グローバルに通用する
- 方法論に中立
SLCPを知る・学ぶ
SLCPについてより深く知り、理解を深めるための情報を順次発信していきます。

- 「国際規格SLCPの進化とそのポイント」
-
国際規格SLCPの2015年版以降では、ハードウェアやソフトウェアの実装は論点でなくなり、上流工程とDevOps的な運用に入ってからの上流へのフィードバックと、保守しやすい構成にするところに論点が移っています。システムとソフトウェアで別々に定義されていたプロセスは、以前から調和が進められてきましたが、明確なシステムの概念が導入され、2015年以降2つのプロセスは同一化されました。
SLCPの全体詳細
JIS和訳版・国際規格原文のご案内
国際規格SLCPの詳細な技術的内容についてはJIS和訳版や原文が参照できます。
現在参照可能な国際規格は以下の通りです。
JIS X 0170:2025システムライフサイクルプロセス(ISO/IEC/IEEE 15288:2023)
- JIS X 0170:2025 システムライフサイクルプロセス(日本規格協会グループ)
- ISO/IEC/IEEE 15288:2023 System life cycle processes(ISO)
JIS X 0160:2021ソフトウェアライフサイクルプロセス(ISO/IEC/IEEE 12207:2017)
- JIS X 0160:2021 ソフトウェアライフサイクルプロセス(日本規格協会グループ)
- ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ソフトウェアライフサイクルプロセス(日本規格協会グループ)
- ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Software life cycle processes(ISO)
書籍「共通フレーム2013」のご案内
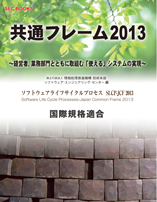
- SEC BOOKS 共通フレーム2013
-
本書は、現行の国際規格SLCPで割愛されている「ソフトウェア固有プロセス」が解説されているため、ソフトウェア開発を重視する場合のプロセス標準として国内では継続して参照されています。
カテゴリ一覧
お問い合わせ先
IPA デジタル基盤センター
-
E-mail
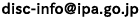
更新履歴
-
2025年9月30日
公開