社会・産業のデジタル変革
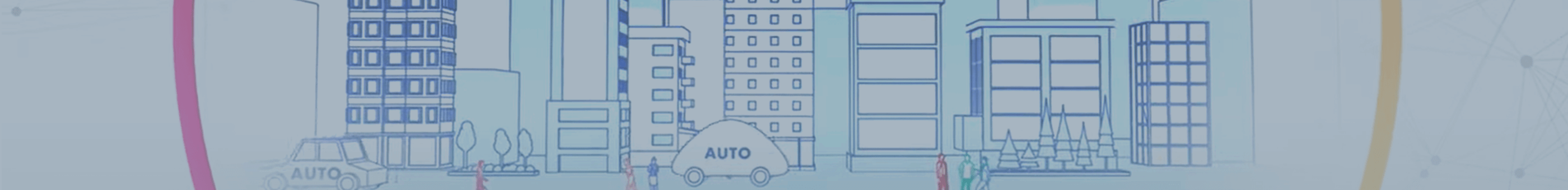
新規・更新申請:設問(1)~(6)
公開日:2025年8月26日
最終更新日:2025年9月12日
独立行政法人情報処理推進機構
デジタル基盤センター
-
G3-010 設問(1)~(3):本設問に対する回答「記載箇所・ページ」
この欄は、「記載内容抜粋」欄の抜粋元を特定するための情報を入力します。
- 公表媒体がウェブページの場合:該当部分を特定できるタイトルや小見出しを入力してください。
- 公表媒体がPDF文書の場合:資料のページ番号を入力してください。ページ番号がない場合は、章タイトルなどを入力してください。
<同じ公表媒体の複数箇所を提示する場合の入力方法>
方法1:1つの回答にまとめて入力する
- 「記載箇所・ページ」を記号(例:「/(スラッシュ)」「;(コロン)」など)や改行で区切って当欄に入力します。
- 回答欄のサイズは、右下の斜め線をドラッグして調整できます。
- 「記載内容抜粋」欄には、各抜粋内容が対応する「記載箇所・ページ」が分かるように入力してください。
方法2:「記載箇所・ページ」ごとに別々の回答を作成する
- 「登録済み公表媒体一覧」から、同じ公表媒体の「回答に使用」ボタンをクリックします。
「記載箇所・ページ」ごとに、別々の回答として作成します。
[よくある不備]
- 設問共通で「記載箇所・ページ」の入力内容が同一の広い範囲で提示されており、設問ごとに抜粋元が特定できない。
- 「記載内容抜粋」欄に抜粋のない「記載箇所・ページ」が入力されている。
-
G3-020 設問(1)~(3):本設問に対する回答「記載内容抜粋」
「記載内容抜粋」欄には、公表媒体に記載されている内容のうち、設問の回答として最も該当する部分を抜粋して入力してください。
認定基準には「公表」が要件として含まれるため、原則として公表媒体からの抜粋が必要です。公表されていない内容の入力は避けてください。入力時のポイント
- 設問の趣旨に沿った代表的な記載内容を抜粋してください。
- 複数の箇所をつなぎ合わせて要約することは可能ですが、文意が変わらないよう注意してください。
- 図表での公表内容は、図表内容を説明してください。
- 抜粋は必要最小限にとどめ、ポイントを絞って入力してください。
- 補足説明を入力する場合は、「補足」であることを明記してください。
ただし、当欄には原則、非公表内容での補足説明は入力できません。非公表内容による補足は「補足説明」欄に入力してください。
補足方法の使い分けについては、「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。
設問(1)の抜粋のポイント
[認定基準のポイント]
データ活用やデジタル技術の進化による社会及び競争環境の変化が自社にもたらす影響(リスク・機会)について認識し、これらを踏まえた「DX推進に向けた経営ビジョン(企業経営の方向性)」と「経営ビジョンの実現に向けたビジネスモデル(情報処理技術活用)の方向性」を入力する。情報処理技術活用の方向性は、DX戦略の方向性を示すものなので、データとデジタル技術活用の観点が含まれている内容を入力してください。
[よくある不備]
情報処理技術活用の方向性として、データとデジタル技術活用の観点が含まれていない、以下のような内容のみが示されている。
事業概要説明、顧客向け事業の方向性、営業戦略、市場拡大戦略等設問(2)の抜粋のポイント
[認定基準のポイント]
設問(1)で提示する経営ビジョンやビジネスモデルを実現するための方策として、DX戦略(データとデジタル技術を活用する戦略)の具体的な取組みを入力する。- 自社業務における変革(DXのX部分)の概要が確認できるように入力してください。
- DXを段階的に推進する計画などもあれば概要を添えてください。
- DX戦略の中で、特に、データ活用の方策の部分を具体的に挙げてください。
例えば、どのようなデータをどのように利活用するか、等を入力してください。 - データ活用にはデジタル技術を用いた取組みの観点も必要です。
[よくある不備]
- DX戦略が方向性のみで具体的な方策の提示がない(設問(1)の方向性と同一内容の提示)。
- ツールの導入やデータ共有の説明のみで、具体的なデータ活用の取組みが確認できない。
- DXやITに関する顧客向けサービスの提供のみの説明となっている。
設問(2)〈1〉の抜粋のポイント
-
注釈機種依存文字の使用を避けるため、設問の丸数字1を〈1〉と表記しています。
[認定基準のポイント]
DX戦略の推進に必要な「体制・組織に関する事項」「デジタル人材育成・確保に関する事項」の両方の内容を入力する。戦略の推進に向けた外部組織との関係構築・協業の方針を定めている場合は、その内容も入力してください。
[よくある不備]
- 体制の提示について、組織図のみが提示され、設問(2)のDX戦略との関連性が不明である。
- 体制・組織のみが提示され、人材育成・確保の内容が不足している。
設問(2)〈2〉の抜粋のポイント
-
注釈機種依存文字の使用を避けるため、設問の丸数字2を〈2〉と表記しています。
[認定基準のポイント]
設問(2)のDX戦略を推進に必要な「ITシステム環境の整備」に向けた方策を入力する。例えば、ITシステムやデータを最新デジタル技術等に連携する環境の整備、DX投資計画、レガシーシステムへの対応(刷新や回避策)等について入力してください。
[よくある不備]
- DX戦略との関連性が不明である。
- DX戦略と同一内容、又はDX戦略を具体的にした内容となっている。
設問(3)の抜粋のポイント
[認定基準のポイント]
設問(2)で提示するDX戦略の達成を測る指標を入力する「指標」の種類として、以下の<1>~<3>の3つの定量指標が、認定基準にて分類されています。
<1>企業価値創造に係る指標(企業が目標設定に用いるあるいはDX戦略的なモニタリング対象とする財務指標)
例:データ活用による営業利益への寄与、デジタルマーケティング活動による売上高の増加など
<2>DX戦略実施により生じた効果を評価する指標
例:工数やコスト削減、品質向上、顧客アプリ利活用での契約数増大、新商品開発件数など
<3>DX戦略に定められた計画の進捗を評価する指標
例:データ活用基盤の社内部門別導入数、各種ITシステムや機能の導入フェーズ達成、顧客向けアプリ利用者数など
その他、達成したか否かが判断できる定性指標が考えられます。
なお、目標値やベンチマークの設定がなされていることが望ましいですが、認定の必須要件とはしません。[よくある不備]
- DX戦略との関連性が不明な指標(特に財務指標)が提示されている。
- DX戦略の内容がそのまま提示されている。
- DX戦略推進に必要な「人材育成・確保」や環境整備の方策に対する指標のみが提示されている。
-
G3-030 設問(1)~(4):補足説明
入力は任意です。
公表情報のみでは説明が難しい場合、公表情報の補足として説明を入力してください。
設問(1)~(4)の認定基準には「公表」が要件として含まれているため、「記載内容抜粋」欄および「発信内容」欄の内容(公表情報)を補うものに限り入力できます。
「補足説明」欄に入力した内容は、申請書に転記されません。事務局での審査時に参考情報として確認します。補足に必要な非公表資料として[添付・連絡]画面から付属資料をアップロードする場合は、「補足説明」欄に、補足説明資料を添付した旨を、参照すべき記載箇所・ページ等とあわせて入力してください。
-
注釈非公表情報による補足説明が多く、認定基準に沿った公表が大幅に不足している場合は不備となります。
-
-
G3-040 設問(4):本設問に対する回答「発信箇所」
申請書の「発信方法」欄には以下の内容が転記されます。
- 回答に選択する公表媒体の「公表媒体(文書等)の名称」欄
- 回答に選択する公表媒体の「公表方法」欄
- 回答に選択する公表媒体の「公表URL」欄または「公表場所」欄
- 当「発信箇所」欄
当「発信箇所」欄 は、「発信内容」欄の抜粋元を特定するための情報を入力します。
- 発信媒体がウェブページの場合:該当部分を特定できるタイトルや小見出しなど発信箇所が分かる情報を入力してください。動画の場合は再生位置も入力してください。
- 発信媒体がPDF文書の場合:資料のページ番号を入力してください。ページ番号がない場合は、章タイトルなどを入力してください。
-
G3-050 設問(4):本設問に対する回答「発信内容」
この欄には、以下の2点を満たす情報発信の内容の概要を入力してください。
- 設問(1)の経営ビジョンや、設問(2)のDX戦略に関する推進や方向性の発信であること
- その発信が、実務執行総括責任者(経営者)本人の名前で行われていること
-
注釈実務執行総括責任者とは、CEO、社長、代表取締役などを想定しています。 それ以外の役職で全社を統括する立場にある場合は、「補足説明」欄にその旨の補足説明を入力してください。
例えば、経営ビジョンやビジネスモデル、DX戦略、DX戦略の推進に必要な各方策、成果指標に基づく成果について、「価値創造ストーリー」として情報発信するなど、公表媒体上で実施された経営者のメッセージやニュースレター等の内容を入力してください。
役職の明記された経営者(実務執行総括責任者)の署名などにより、発信者が公表媒体上で確認できる内容とし、経営者自らのメッセージを抜粋して具体的に入力してください。(例えば、DX戦略の内容そのものに、署名があるだけの内容は入力できません。)(事業者内部での発信内容も対象外です。)
記入のポイント
- DX戦略との関連性を明確にしてください。
- 発信内容の要点を簡潔にまとめて入力してください。
- 単なる方針の再掲ではなく、推進の意志や姿勢が伝わるメッセージであることが必要です。
[よくある不備]
- 社内向けなど、対外的に公開されていない内容を提示している。
- 発信者の氏名や役職が不明確で、経営者による発信と確認できない。
- 単にDX戦略の公表資料を提示しており、経営者自身の発信と読み取れない。
-
G3-060 設問(5):実施時期
設問文に対する実施期間として、おおよその開始年月と終了年月を入力してください。
開始年月の入力は必須です。
申請時点で継続して実施中の場合、終了年月の入力は不要です。終了年月が空欄の場合、申請書には「継続実施中」と表記されます。更新申請においては、前回の認定適用時以降で最も直近に実施した課題把握の内容を提示する必要があるため、最新の課題把握実施時期を含む年月を入力してください。
[よくある不備]
- 【更新申請】終了年月が前回の認定適用時より前であり、認定適用時以降の最新の課題把握実施時期を含んでいない。
-
G3-070 設問(5):実施内容[1]
「[1]「DX推進指標」による自己分析を行い、DX推進ポータルの「DX推進指標」メニューから提出済み。」を選択した場合は、提出時の受付番号(16桁の英数字)を入力してください。
本申請では、「DX推進指標」の自己診断結果をあらためて添付する必要はありません。-
注釈入力された受付番号が存在しない場合、エラーメッセージが表示され、申請を完了できません。
更新申請においては、前回の認定適用時以降で最も直近に実施し提出した、「DX推進指標」自己診断結果の受付番号の入力が必要です。
- 関連リンク
-
-
G3-080 設問(5):実施内容[2]
「[2]「DX推進指標」による自己分析を行い、本申請に添付して提出する。」を選択した場合は、自己診断結果をフォームにアップロードしてください。「DX推進指標」による自己分析を実施しているものの、DX推進ポータルの「DX推進指標」メニューを利用しない場合が対象です。
フォームにはIPAで配布している「DX推進指標自己診断フォーマット」(Excel)に、自己診断結果を入力したファイルのみをアップロードできます。更新申請においては、前回の認定適用時以降で最も直近に実施した、「DX推進指標」自己診断結果のアップロードが必要です。
<ファイルのアップロードができない場合の対処方法>
お使いのネットワーク環境やパソコンなどに導入されているセキュリティソフトにより、ファイルのアップロードに失敗する場合があります。
以下の項目について、設定などのご確認をお願いします。通信許可を必要とするURL
https://filemanager.dx-portal.ipa.go.jp (GET および POST の通信を許可)- 関連リンク
-
G3-090 設問(5):実施内容[3]
「[3]「DX推進指標」以外を用いた、独自の課題把握を行っている。」を選択した場合は、課題把握の結果が分かる資料をアップロードしてください。
そのうえで、次の2点の説明を入力してください。
- 実務執行総括責任者(経営者)のリーダーシップの下で、課題把握を実施していること
- 課題把握として実施した内容の概要
-
注釈実務執行総括責任者とは、CEO、社長、代表取締役などを想定しています。代表権を有するCEOや社長(他の代表取締役を含む)以外の役職の方が実務執行統括責任者に該当する場合は、その理由や社内での位置づけを、「補足説明」欄にて説明してください。
なお、アップロードした資料のうち、課題把握の結果が記載されている箇所の情報(ページ番号や見出し等)を、「補足説明」欄に入力してください。
更新申請においては、前回の認定適用時以降で最も直近に実施した、課題把握結果の分かる資料をアップロードする必要があります。
<ファイルのアップロードができない場合の対処方法>
お使いのネットワーク環境やパソコンなどに導入されているセキュリティソフトにより、ファイルのアップロードに失敗する場合があります。
以下の項目について、設定などのご確認をお願いします。通信許可を必要とするURL
https://filemanager.dx-portal.ipa.go.jp (GET および POST の通信を許可)
-
G3-100 設問(5):補足説明
「補足説明」欄に入力した内容は、申請書に転記されません。事務局での審査時に参考情報として確認します。
[3]を選択した場合は、課題把握の結果が分かる資料の参照箇所(ページ番号や見出し等)を必ず入力してください。そのうえで、取組みの補足説明が必要な場合は任意で入力してください。
[1]、[2]の「DX推進指標」を用いた課題把握を選択した場合は、任意で取組みの補足説明を入力してください。
-
G3-110 設問(6):実施時期
設問文に対する実施期間として、おおよその開始年月と終了年月を入力してください。
開始年月の入力は必須です。
申請時点で継続して実施中の場合、終了年月の入力は不要です。終了年月が空欄の場合、申請書には「継続実施中」と表記されます。更新申請においては、前回の認定適用時以降の最新の実施状況に基づいて実施時期を更新してください。
[よくある不備]
- 【更新申請】終了年月が前回の認定適用時より前であり、認定適用時以降の最新の実施状況を含んでいない。
-
G3-120 設問(6):実施内容
サイバーセキュリティ経営ガイドライン等に基づき、策定および実施されたサイバーセキュリティ対策の内容を入力してください。公表媒体に基づく説明は求められていません。
例えば、セキュリティ基本方針の策定、データの暗号化、アクセス制御やアクセスログの管理、セキュリティ対策の専門家の配置、社員へのセキュリティ教育実施等、対策の策定および実施内容そのものを提示する必要があります。
なお、セキュリティ監査の概要説明は別途設けている専用の回答欄に入力してください。セキュリティ監査は、サイバーセキュリティ対策を実施したうえで行うものであるため、対策の説明と監査の説明の回答欄を区別しています。<SECURITY ACTION制度に基づく自己宣言(二つ星)を行っている場合>
中小企業、小規模企業、個人事業主においては、「SECURITY ACTION自己宣言(二つ星)」を宣言していることが確認できる場合、当欄へのサイバーセキュリティ対策の実施内容および監査概要欄への入力を省略できます。 この場合は、「SECURITY ACTION制度に基づき自己宣言(二つ星)を行っている。」にチェックを付けてください。「実施内容」欄に所定の文言が自動で挿入されます。
審査においては、原則、IPAの専用サイトへの掲載状況を確認します。- 関連リンク
-
G3-130 設問(6):監査概要/SECURITY ACTION自己宣言ID
当欄に入力した内容は、申請書に転記されません。ただし、認定基準に基づく確認事項であるため、審査の対象です。
次のいずれかの方法により実施済みのセキュリティ監査等の概要説明を入力してください。
- 監査等の概要説明(監査目的、監査対象、監査の実施期間、監査実施者[もしくは内部監査・外部監査の別]、採用した監査手続きの概略)を「監査の概要」欄に入力する。(実施済みのセキュリティ監査等に関する報告書や説明資料のアップロードは任意)
- 実施済のセキュリティ監査等の説明文書を「実施済みのセキュリティ監査等に関する報告書や説明資料アップロード」フォームからアップロードし、「監査の概要」欄では、当該文書の参照箇所(ページ番号や見出し等)を入力する。
更新申請においては、前回の認定適用時以降で最も直近に実施したセキュリティ監査の説明を入力する必要があります。前回の認定適用時以降に、セキュリティ監査を実施していない場合は、前回の認定適用時に提示した監査概要が最新であることの明記が必要です。
<SECURITY ACTION制度に基づく自己宣言(二つ星)を行っている場合>
中小企業、小規模企業、個人事業主において、「実施内容」欄で「SECURITY ACTION制度に基づき自己宣言(二つ星)を行っている。」にチェックを付けた場合は、SECURITY ACTION自己宣言(二つ星)のお申し込み後に通知される自己宣言ID(11桁の数字)を入力してください。<ファイルのアップロードができない場合の対処方法>
お使いのネットワーク環境やパソコンなどに導入されているセキュリティソフトにより、ファイルのアップロードに失敗する場合があります。
以下の項目について、設定などのご確認をお願いします。通信許可を必要とするURL
https://filemanager.dx-portal.ipa.go.jp (GET および POST の通信を許可) - 監査等の概要説明(監査目的、監査対象、監査の実施期間、監査実施者[もしくは内部監査・外部監査の別]、採用した監査手続きの概略)を「監査の概要」欄に入力する。(実施済みのセキュリティ監査等に関する報告書や説明資料のアップロードは任意)
-
G3-140 設問(6):補足説明
入力は任意です。
「補足説明」欄に入力した内容は、申請書に転記されません。事務局での審査時に参考情報として確認します。
「実施内容」欄に入力したサイバーセキュリティ対策の策定および実施内容について、必要に応じて補足説明を入力してください。
更新履歴
-
2025年9月12日
G3-080、G3-090、G3-130 内容修正
-
2025年8月26日
本ページを公開
