デジタル人材の育成

情報処理安全確保支援士(登録セキスぺ)に関するよくあるご質問
公開日:2023年4月3日
最終更新日:2025年12月3日
(注釈)本文書中の「ポータルサイト」は「情報処理安全確保支援士ポータルサイト」を示します。
1.制度全般に関すること
-
Q1-1.情報処理安全確保支援士になることができる人は誰ですか?
情報処理安全確保支援士の欠格事由(関連事項:Q1-2)に該当しない方で、「情報処理安全確保支援士試験」に合格された方及び「情報処理安全確保支援士試験合格者と同等以上の能力を有する者」(関連事項:Q1-3)として経済産業大臣が認める方が、情報処理安全確保支援士の登録を受けることができます。
-
Q1-2.「情報処理安全確保支援士の欠格事由」とはどのようなものですか?
情報処理の促進に関する法律(以下、「情促法」といいます。)第5条により、次のいずれかに該当する場合は、情報処理安全確保支援士になることができないとされています。
- 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 情促法の規定、刑法第168条の2及び第168条の3の規定並びに不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条、第9条及び第10条の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 情促法第16条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
-
Q1-3.「情報処理安全確保支援士試験合格者と同等以上の能力を有する者」とはどのような人ですか?
情報処理の促進に関する法律施行規則第一条に規定する経済産業大臣の認定について定める告示(2017年4月7日経済産業省告示第94号、2017年9月29日経済産業省告示第227号)に定められているように、「警察、自衛隊、内閣官房および情報処理安全確保支援士試験委員でセキュリティ関連業務に従事し、経済産業大臣が認定した者」またはIPAの「産業サイバーセキュリティセンターが行う中核人材育成プログラムを終了し、1年以内に登録を受ける者」となります。
-
Q1-4.情報処理安全確保支援士としての義務に違反した場合は、どうなりますか?
情報処理安全確保支援士としての義務(信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、講習受講義務)に違反した場合は、経済産業省により「資格名称の使用の停止」又は「登録の取消し」の処分が命じられる場合があります。
- 情報処理安全確保支援士試験合格者
- 資格名称の使用の停止の場合は、経済産業大臣がその期間を定めることとなっておりますので、基本的には期間満了をもってその状態から復帰することになります。
- 登録を取り消された場合は、2年間は再登録できません。
なお、情報処理安全確保支援士試験の合格そのものは有効ですので、再登録の際に再度情報処理安全確保支援士試験に合格していただく必要はございませんが登録免許税、登録手数料、その他書類は再度必要です。
- 経過措置対象者(注釈)
- 資格名称の使用の停止については、1と同様です。
- 登録を取消された場合は、新たに情報処理安全確保支援士試験に合格し、再度登録手続きをしていただく必要があります。
(注釈)「情報セキュリティスペシャリスト試験」及び「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」合格者で、平成30年10月1日までに「情報処理安全確保支援士」に登録された方。
- 情報処理安全確保支援士試験合格者
-
Q1-5.登録を辞めたいのですが何か手続きは必要ですか?
「情報処理安全確保支援士登録消除届出書」に必要事項を入力または記入のうえ、登録証(カード型)の原本を同封し、郵送にてお送りください(郵送のみの対応となります)。
様式については、「変更等の各種申請」をご参照ください。
なお、2020年4月以前に発行された紙の登録証は無効です。
2.新規登録に関すること
-
Q2-1.登録申請の手続きを教えてください。
登録申請の手続きや必要となる書類につきましては、「情報処理安全確保支援士登録の手引き」をご参照ください。
-
Q2-2.情報処理安全確保支援士試験に合格した後、登録期限はありますか?また、登録しない場合、試験合格は無効になりますか?
登録の期限はありません。また、登録しないことにより試験合格が無効になることはありません。ただし、登録をしないと、「情報処理安全確保支援士」の名称を使用することはできませんのでご注意ください。(情報処理安全確保支援士でない方が資格名称を使用した場合、30万円以下の罰金となります。)
-
Q2-3.登録申請書は、両面印刷する必要はありますか?
両面印刷、片面印刷どちらでも構いません。
-
Q2-4.登録申請書を作成時、二次元コードが作成されませんがどうしたらよいでしょうか?
ブラウザ上で開いたまま入力できません。そのため、二次元コードの作成もされません。必ずファイルをダウンロードして一度保存してから入力してください。
-
Q2-5.登録申請書を印刷した後間違いに気づいて修正しました。印刷した用紙は1ページ目だけの差し替えで問題ないですか?
全て差し替えてください。登録申請書にある「申請書印刷」ボタンを押下すると、登録申請書に記入された内容が二次元コード化され2ページ目の二次元コード表示エリアに表示されます。そのため、登録申請書の記入内容を修正した場合は、「申請書印刷」ボタンを再度押下した上で印刷をして全て差し替えたうえで提出してください。また、やむをえない場合を除いて、登録申請書への入力はパソコンで行ってください。ただし、外字を使用する等の場合は印刷後に黒色のボールペンで手書きしてください。こすると消えるタイプのボールペンや、シャープペンシルなど消去可能な筆記具の使用は避けてください。
また、修正液や修正テープなどによる訂正も行わないようお願いします。記録が消えず、改変の痕跡が残らない筆記具をご使用ください。 -
Q2-6.登録申請書に貼り付ける登録免許税の収入印紙に押印(割印)は必要ですか?
絶対に押印(割印)をしないでください。押印されると、収入印紙が無効となります。
-
Q2-7.「住民票」はどこまでの表記が必要ですか?
ご提出いただく住民票は、申請者個人のもので、「世帯主・続柄」、「本籍・筆頭者」の記載は省略していただいて構いません。
-
Q2-8.誓約書の自署を記入の際に注意する点はありますか?
パソコンの入力ではなく、必ず黒のボールペンで自署してください。こすると消えるタイプのボールペンや、シャープペンシルなど消去可能な筆記具の使用は避けてください。
また、修正液や修正テープなどによる訂正も行わないようお願いします。記録が消えず、改変の痕跡が残らない筆記具をご使用ください。 -
Q2-9.「登録事項等公開届出書」で提出した内容を変更することは可能でしょうか?
登録申請後、登録証交付前までの間に変更する場合は「登録事項等公開届出書」に変更後の内容を入力または記入の上、郵送により再提出をお願いします。再提出された内容が有効となります。登録後はポータルサイトよりオンライン申請を行ってください。
-
Q2-10.登録するためには、費用はいくらかかりますか?
登録のためには、登録免許税(9,000円)と登録手数料(10,700円)の納付が必要となります。登録免許税(9,000円)は、郵便局等で「収入印紙」を購入し、登録申請書に貼付してください。また、登録手数料(10,700円)については、IPAの指定する銀行口座にお振込みいただき、その証明書類を登録申請書に貼り付けする方法で納付してください。
-
Q2-11.登録手数料を会社負担としたいのですが、会社口座から振り込むことは可能でしょうか?また、複数人分をまとめて振り込むことは可能でしょうか?
会社口座から振り込むことは可能です。1人分の登録手数料を振り込む場合は、会社名義で振込後、「情報処理安全確保支援士登録の手引き」に従って登録申請を行ってください。また、複数人分をまとめて振り込む場合は、個別にお問い合わせください。
-
Q2-12.領収書は発行できますか?
登録手数料分(10,700円)は登録証に同封して郵送しています。詳しくは「情報処理安全確保支援士登録の手引き」(p.7【領収書】)をご参照ください。なお、登録免許税分(9,000円)はIPAでは発行できませんので、申請者ご自身により、収入印紙を購入した際の領収書を保管のうえ、ご対応ください。
-
Q2-13.領収書の再発行はできますか?
登録手数料の領収書を紛失した場合や宛名の変更等で再発行を希望する場合は、登録日(4月1日または10月1日)から1年を期限として再発行が可能です。
再発行の手続き等をご案内しますので、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
IPA デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ
- E-mail:
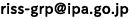
-
Q2-14.登録証の再交付はできますか?
登録証を滅失や汚損・破損した際は再発行が可能です。詳しくは「情報処理安全確保支援士登録の手引き」(p.193.登録証の再交付)をご参照ください。
-
Q2-15.登録申請後に住所の変更、勤務先名の変更などがあった場合は、どうしたらいいですか?
登録申請後、登録証交付前までの間に変更する場合は「情報処理安全確保支援士連絡先等変更届出書」に、変更前後の内容を入力の上、郵送により提出をお願いします。登録後はポータルサイトよりオンライン申請を行ってください。
登録事項の変更方法は「変更等の各種申請」をご参照ください。 -
Q2-16.経過措置対象者の場合、登録が取り消されたあとに再登録は可能でしょうか?
経過措置対象者の場合、登録申請できるのは2年間です(平成30年8月19日に申請を締切りました)。登録が取り消された場合は、その後2年間登録ができませんので、再登録するためには、新たに情報処理安全確保支援士試験に合格することが必要となります。(関連事項:Q1-4)
-
Q2-17.公的書類(住民票など)に有効期限はありますか?
発行から3か月以内のものをご提出ください。
-
Q2-18.海外勤務のため国内での郵便物が受け取れません。国外(勤務地)へ郵送してもらうことはできますか?
日本国外への郵送はできません。国内での郵便物の受取代理人を選定のうえ「郵便物受取代理人設定届出書」の提出をお願いします。登録後はポータルサイトよりオンライン申請を行ってください。
-
Q2-19.登録申請の際に以前は「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の提出が必要でしたが、提出は不要となったのでしょうか?
2019年9月14日施行「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、2020年4月登録から、新規登録時の提出書類のうち「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の提出が不要となりました。
-
Q2-20.登録申請書の記入・提出に関する注意事項を教えてください。
登録申請書をご提出いただく際は、以下の点にご留意ください。
- 記入方法について
- 申請書は 原則としてパソコン入力・印刷にてご記入ください。
一部、漢字変換ができない氏名など、パソコン入力が困難な箇所については、印刷後に 手書きで記入していただいて構いません。
- 申請書は 原則としてパソコン入力・印刷にてご記入ください。
- 手書き記入時の注意点
- 外字を使用する等の場合は印刷後に黒色のボールペンで手書きしてください。
こすると消えるタイプのボールペンや、シャープペンシルなど消去可能な筆記具の使用は避けてください。
また、修正液や修正テープなどによる訂正も行わないようお願いします。記録が消えず、改変の痕跡が残らない筆記具をご使用ください。
時間の経過や保管環境により、インクが薄くなる・消える可能性があります。耐光性・耐水性のある筆記具を推奨します。
- 外字を使用する等の場合は印刷後に黒色のボールペンで手書きしてください。
- 印字の濃度について
- 印刷時に文字が薄くなっている場合は、再印刷の後、ご提出をお願いいたします。
- 記入方法について
3.更新に関すること
-
Q3-1.更新期限はありますか?
更新期限は、直近の登録日または更新日から起算して3年となります。
-
Q3-2.登録更新の申請をするのに、期限はありますか?
「登録更新申請期限」は、更新期限(関連事項:Q3-1)の60日前までです。
「登録更新申請期限」までにオンラインによる登録更新申請を行う必要があります。(関連事項:Q3-4)
登録日別の登録更新サイクルにつきましては「情報処理安全確保支援士 登録日・更新日別 講習受講および登録更新サイクル 早見表」にてご確認をお願いします。
-
Q3-3.登録更新申請するための条件を教えてください。
「登録更新申請期限」までに次の1、2を満たすことが条件です。
- 講習受講を修了していること
- オンライン講習3回、IPAまたは民間事業者等が行う実践講習1回を全て受講修了する必要があります。(関連事項:Q4-1)
- 講習受講についての詳細は「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の受講する講習について」を参照ください。
- 登録更新申請を行っていること(関連事項:Q3-2、Q3-4)
- 講習受講を修了していること
-
Q3-4.登録更新申請の手続きはどのようにしたらよいですか?また費用はかかりますか?
- ポータルサイトより登録更新申請を行ってください。
- 手続きの詳細については、ポータルサイトの右サイドバーにある「更新」をご参照ください。
- また、更新するための費用はかかりません。
-
Q3-5.登録更新しなかった場合、どうなりますか?試験の合格も無効になりますか?
登録更新申請期限までに登録更新申請されなかった場合、更新期限の翌日付で資格失効となります。なお、更新しない場合においても試験合格は有効です。
-
Q3-6.登録更新しなかった場合、後日再登録は可能でしょうか?
- 再登録は可能です。ただし経過措置対象者(注釈)は、登録消除後に再登録はできません。情報処理安全確保支援士試験に合格すれば、登録が可能になります。
- (注釈)「情報セキュリティスペシャリスト試験」及び「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」合格者で、平成30年10月1日までに「情報処理安全確保支援士」に登録された方。
-
Q3-7.登録更新しない予定ですが、手続きはありますか?
「情報処理安全確保支援士登録消除届出書」を更新期限までに提出ください。登録事項の変更方法は「変更等の各種申請」をご参照ください。
-
Q3-8.登録更新申請時に登録事項を変更できますか?
登録更新申請時に登録事項を変更することはできません。登録事項の変更方法は「変更等の各種申請」をご参照ください。
-
Q3-9.登録更新申請後に住所の変更、勤務先名の変更などがあった場合は、どうしたらいいですか?
ポータルサイトより「情報処理安全確保支援士連絡先等変更届出書」にて変更内容を申請してください。
登録事項の変更方法は「変更等の各種申請」をご参照ください。
-
Q3-10.新しい登録証を受領後、古い登録証はどうしたらいいですか?
新しい登録証を受領後、古い登録証は個人情報に配慮した形で破棄またはIPAに返送してください。
-
Q3-11.海外勤務のため国内での郵便物が受け取れません。国外(勤務地)へ郵送してもらうことはできますか?
日本国外への郵送はできません。国内での郵便物の受取代理人を選定のうえ、ポータルサイトより郵便受取代理人申請を行ってください。
4.情報処理安全確保支援士の受講する講習に関すること
-
Q4-1.情報処理安全確保支援士の講習受講義務とはどのようなものですか?
次の1、2になります。
- 直近の登録日または更新日から3年以内に、オンライン講習を3回(1回/年)受講修了
- 直近の登録日または更新日から3年以内に、IPAまたは民間事業者等が行う実践講習の中からいずれか1つを1回受講修了
-
Q4-2.講習の内容はどのようなものですか?
次の1、2、3になります。
- サイバーセキュリティに関する知識:攻撃手法及びその技術的対策、情報セキュリティ関連制度等の概要及び動向
- サイバーセキュリティに関する技能:脆弱性・脅威の分析、情報セキュリティ機能に関する企画・要件定義・開発・運用保守、インシデント対応、情報セキュリティ管理支援
- 情報処理安全確保支援士として遵守すべき倫理:倫理的責任と義務、法令遵守・契約履行
最新の動向を反映するべく教材の見直しも毎年行っています。
-
Q4-3.実践講習A、実践講習B、実践講習Cは、非集合型のリモート形式での講習(リモート講習)とのことですが、いつでも受講は可能ですか?また、どこでも受講可能ですか?
実践講習A、実践講習B、実践講習Cは、Web会議システムを用いた「グループ討議」を中心とした講習で、その事前準備として、e-ラーニングでの「個人学習」をあわせて受講頂く講習です(詳細は、「IPAが行う実践講習」をご参照ください)。
- 受講日について
- 「個人学習」は、申込手続き後、受講可能になります。
- 「グループ討議」は、申込時に「グループ討議」開催日程から選択した受講日にのみ受講可能です。
- なお、「個人学習」は、「グループ討議」参加日までに受講完了する必要があります。
- (注釈)リモート講習の申込は、講習運営者からの案内をご確認ください。講習運営者の一覧は、以下のPDFよりご覧いただけます。
- 講習運営者一覧(PDF:173 KB)
- 受講場所について
- 「個人学習」は、e-ラーニング形式ですので、学習場所は問いません。
- 「グループ討議」は、リモート形式でディスカッションを行いますので、周囲の雑音の影響のない自宅、会社の会議室、サテライトオフィス等での受講をお願いいたします。オープンスペースでの受講や、移動しながらの受講の場合は、受講をお断りする場合がありますので、ご了承ください。
- 受講日について
-
Q4-4.講習を受講するためには、費用はいくらかかりますか?
オンライン講習は2万円、実践講習は受講する講習により異なります。
IPAが行う実践講習については、IPAが行う実践講習をご覧ください。
なお、民間事業者等が行う実践講習については、講習実施機関が定めた受講料となります。 -
Q4-5.講習受講料は事前に3年分一括して支払う必要がありますか?
- 講習受講料のお支払いは、3年分事前に一括ではなく各講習を受講していただくタイミングとなります。
- お支払い方法や手続きの詳細については、講習運営者から送付されるメールをご確認ください。講習運営者の一覧は、以下のPDFよりご覧いただけます。
- 講習運営者一覧(PDF:173 KB)
-
Q4-6.講習受講料を会社から支払うことはできますか?
講習受講義務は、情報処理安全確保支援士個人に課せられます。
オンライン講習及び実践講習A、実践講習B、実践講習Cについては、講習のお申し込みやお支払いは個人での処理を原則とします。(所属企業が費用負担をする場合は、情報処理安全確保支援士ご本人が立替え払いののち、社内で精算していただくことを原則とします。)
ただし、登録・更新時期および申込対象講習により、法人名義でお支払いいただくことも可能です。- オンライン講習
- 法人名義でのお支払いについては、団体アカウントを作成し、団体コード、支払いトークンを取得することが必要です。
- 手続きの詳細については、ポータルサイトの右サイドバーにある「オンライン講習」の「受講料を所属団体がお支払いする場合」をご参照ください。
- なお、法人振込の場合は、情報処理安全確保支援士の照合に時間を要する可能性があります。
- 当手続きが完了するまでは受講を開始できませんので、ご了承ください。
- 実践講習A、実践講習B、実践講習C
- 手続き方法については、情報処理安全確保支援士ご本人宛に送付された、講習運営者からの案内メールをご確認ください。講習運営者の一覧は、以下のPDFからご覧いただけます。
- 講習運営者一覧(PDF:173 KB)
- なお、法人振込の場合は、情報処理安全確保支援士の照合に時間を要する可能性があります。
- 当手続きが完了するまでは受講を開始できませんので、ご了承ください。
- その他の講習については、各講習の運営者へ直接お問い合わせください。
講習の運営者一覧は、以下のPDFよりご確認いただけます。 - 講習運営者一覧(PDF:173 KB)
- オンライン講習
-
Q4-7.講習受講料の領収書は発行できますか?また、再発行はできますか?
- オンライン講習の場合:
- ポータルサイトの講習システムにて発行できます。再発行も可能です。
- ただし、ポータルサイトの講習システム以外で受講した講習の領収書の発行や再発行はできません。
- 実践講習A、実践講習B、実践講習Cの場合:
- 領収書の発行は再発行を含めて可能ですが、発行期限がございます。具体的な発行方法、発行期限は講習運営者にお問い合わせください。
- なお、現在領収書が発行可能な講習は、以下の「講習運営者一覧」に記載されている講習運営者の提供期間内に受講したもののみとなります。
- 期間外の受講日の領収書発行および再発行はできません。(旧集合講習およびこれに類する講習を含む)
- 講習運営者一覧(PDF:173 KB)
- 業界別サイバーレジリエンス強化演習(CyberREX)、制御システム向けサイバーセキュリティ演習(CyberSTIX)の場合:
- 講習運営者にお問い合わせください。講習運営者の一覧は、以下のPDFからご覧いただけます。
- 講習運営者一覧(PDF:173 KB)
- 民間事業者等が行う実践講習の場合:
- 各講習実施機関にお問い合わせください。
- お問い合わせ
- 各種お問い合わせ先 > 講習に関するお問い合わせ > 民間事業者等が行う実践講習
- オンライン講習の場合:
-
Q4-8.障がいを持つ場合でも講習は受講できますか?
オンライン講習及び実践講習については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行います。
受講に際しての配慮をご希望の場合は、事前に以下までご連絡ください。オンライン講習、実践講習A、実践講習B、実践講習C
IPA デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ- E-mail:
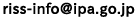
業界別サイバーレジリエンス強化演習(CyberREX)、制御システム向けサイバーセキュリティ演習(CyberSTIX)
IPA 産業サイバーセキュリティセンター- E-mail:
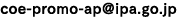
民間事業者等が行う実践講習
各講習実施機関にお問い合わせください。
-
Q4-9.期限までに情報処理安全確保支援士の講習を受講しなかった場合はどうなりますか?
経済産業省により「資格名称の使用の停止」又は「登録の取消し」の処分が命じられる場合があります。
詳細は、Q1-4をご参照ください。 -
Q4-10.オンライン学習期間(学習開始後3ヵ月)が超過してしまい、修了することができませんでした。どうすればよいですか?
再度、受講料を支払った上で受講してください。なお、それまでに受講した受講履歴は引き継がれませんので、オンライン学習期間内に受講が修了するよう、計画的に受講してください。
-
Q4-11.講習修了証はいつ発行されますか?
- オンライン講習は受講修了後に、IPAが行う実践講習は講習修了日(注釈)の翌月末を目途に、ポータルサイトの講習システムからPDF形式でダウンロードが可能です。民間事業者等が行う実践講習の修了証については、講習実施機関にお問い合わせください。
- (注釈)実践講習A・B・Cについてはグループ討議受講後、5営業日以内の日
-
Q4-12.講習修了証の再発行はできますか?
講習修了証の再発行はできませんが、「講習修了証明書」の発行はできます。
-
Q4-13.情報処理安全確保支援士検索サービスの講習修了年月日は、いつ更新されますか?
原則として、講習修了月の翌月末に更新されます。
-
Q4-14.既に登録を受けている人が、講習の受講に代えて、情報処理安全確保支援士試験に再度合格することで、資格を維持することはできますか?
既に登録を受けている情報処理安全確保支援士の方が、情報処理安全確保支援士試験に再度合格し、その合格をもって新たに登録手続きを行うことは可能です。この場合の手続きや講習受講義務の取扱いは以下のとおりとなります。
- 新たな合格をもって登録する際には、新規登録の扱いとなります。従前の登録に係る消除申請(情報処理の促進に関する法律施行規則第24条)と新規の登録申請を同時に行う必要があります。その際、改めて登録免許税、登録手数料の納付も必要となります。
- この場合の消除申請に限り、業を廃止しようとする日(従前の登録の消除日)が新しい登録日の前日となりますので、実質的に登録期間を継続した状態とすることができます。
- 登録年月日及び登録番号は新しいものになります。
- 登録を受けている間は、法令に定められた内容に応じ所定の講習の受講義務が生じますが、消除申請により業を廃止した日をもって、その登録に係る講習受講義務は消滅します。
- ご不明な点は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
IPA デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ
- E-mail:
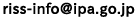
5.情報処理安全確保支援士の名乗り方・名刺表記・ロゴマークの利用に関すること
-
Q5-1.いつから「情報処理安全確保支援士」を名乗ってよいのですか?
登録簿への登録を受けた時点からとなります。通常4月1日又は10月1日からとなります。
-
Q5-2.履歴書や名刺への書き方を教えてください。
情報処理安全確保支援士の方は、「情報処理安全確保支援士(通称 登録情報セキュリティスペシャリスト〔登録セキスペ〕)」の名称を履歴書や名刺等へ記載することが可能です。
情報処理安全確保支援士のロゴマークを掲示する場合は、「情報処理安全確保支援士ロゴマーク」利用規約に従って、登録番号の併記が必須となります。(登録番号の6桁の数字は必ず記載ください。)資格名称を掲示する場合は、偽って名乗っていないことの証明のため、登録番号の表記をすることを推奨します。【資格名称記載例】
「XXXXXX」は登録番号の6桁の数字を表しています。- 日本語表記
- 情報処理安全確保支援士(【登録番号(注釈1)】)
- 登録情報セキュリティスペシャリスト(【登録番号(注釈1)】)
- 注釈1【登録番号】の表記例:登録番号 XXXXXX、登録番号第XXXXXX号、第XXXXXX号、XXXXXX
- 英語表記
- RISS (【Registered No. (注釈2)】)
- Registered Information Security Specialist (【Registered No. (注釈2)】)
- 注釈2【Registered No.】の表記例:Registered No. XXXXXX、XXXXXX
情報処理安全確保支援士のロゴマークを掲示する場合の併記方法については、ロゴマークの利用についてをご確認ください。
なお、情報処理安全確保支援士試験の合格後、未登録の方については、「情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験」試験に関するよくある質問(その他)をご参照ください。
- 日本語表記
-
Q5-3.情報処理安全確保支援士のロゴマークは誰が利用できますか?また、いつから利用可能ですか?
主に利用可能な方は次の通りです。
- 情報処理安全確保支援士(有資格者) ご本人
- 情報処理安全確保支援士の所属する組織、企業
- (報道関係者・学校関係者その他の方が法令に基づいて本ロゴを適法に使用することを妨げません)
- それぞれの利用規約をご参照の上、すべての事項に同意いただいた場合は利用可能です。
1の方が、自身が資格保持者であることを示すために利用(名刺への印刷等)する場合は、登録簿への登録を受けた時点から利用可能となります。
2の方は、情報処理安全確保支援士ロゴマーク利用規約_2をご確認のうえ、以下のフォームから申請してください。
情報処理安全確保支援士ロゴマークの利用申請書(新規)受付フォーム
情報処理安全確保支援士ロゴマークの利用申請書(変更)受付フォーム
(注釈)受付フォームは外部サービス(WEBCAS)を利用しています。
詳細はロゴマークの利用についてをご覧ください。
-
Q5-4.情報処理安全確保支援士本人の名刺に情報処理安全確保支援士のロゴマークを印刷する場合、利用申請書の提出は必要ですか?
利用申請書の提出は不要です。名刺に情報処理安全確保支援士のロゴマークを印刷する場合に該当する利用規約は、「(1)本人向け」となるためです。
-
Q5-5.自社に情報処理安全確保支援士がいる場合、社員全員の名刺に情報処理安全確保支援士のロゴマークを印刷することはできますか?
印刷できません。情報処理安全確保支援士本人の名刺のみ情報処理安全確保支援士のロゴマークを印刷できます。(登録番号の併記が必須)
6.徽章に関すること
-
Q6-1.徽章貸与申請の手続きを教えてください。
ポータルサイトに掲載の「徽章の手引き」をご参照のうえ、ポータルサイトより徽章貸与申請を行ってください。
-
Q6-2.徽章貸与申請するための条件を教えてください。
次の1.2.3.を全て満たすことが条件です。
- 申請時点で、情報処理安全確保支援士として登録されている方
- 徽章の貸与を受けていない方
- 情報処理安全確保支援士徽章利用規約に同意し、遵守できる方
-
Q6-3.情報処理安全確保支援士への登録前に貸与申請はできますか?
情報処理安全確保支援士に登録されている方のみ貸与申請が行えます。登録前に貸与申請は出来ません。
-
Q6-4.複数の徽章の貸与を受けることはできますか?
徽章の貸与は、一人につき一個です。
-
Q6-5.徽章を貸与するためには、費用はいくらかかりますか?
貸与手数料(2,970円(税込))の納付が必要となります。クレジットカード、銀行決済(Pay-easy)または、コンビニ決済で納付してください。なお、銀行決済(Pay-easy)は176円(税込)、コンビニ決済は189円(税込)の決済手数料が追加で必要となります。
-
Q6-6.貸与手数料・再貸与手数料の領収書は発行できますか?
貸与手数料・再貸与手数料の領収書はポータルサイトにて発行できます。
-
Q6-7.情報処理安全確保支援士でなくなった場合、貸与を受けていた徽章はどうすればよいですか?
徽章はIPAの資産です。情報処理安全確保支援士でなくなった場合は、速やかにIPA宛に返却してください。
-
Q6-8.海外勤務のため国内での郵便物が受け取れません。国外(勤務地)へ郵送してもらうことはできますか?
日本国外への郵送はできません。国内での郵便物の受取代理人を選定のうえ、ポータルサイトより郵便受取代理人申請を行ってください。
7.その他
-
Q7-1.登録手数料、講習受講料等は消費税の課税対象ですか?
情報処理安全確保支援士試験受験手数料、登録手数料、IPAの行う講習受講料は非課税です。
徽章の貸与手数料、再貸与手数料は課税対象です。
-
Q7-2.領収書はインボイス制度に対応していますか?
領収書は、適格請求書(インボイス制度)の要件を満たしています。
