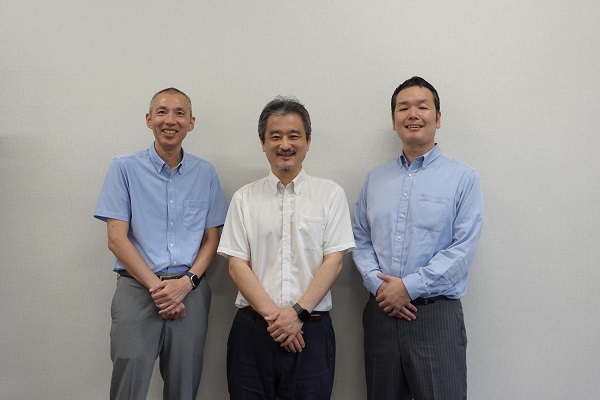デジタル人材の育成

ペンギンシステム株式会社 インタビュー
公開日:2025年7月15日
最終更新日:2025年9月25日
ペンギンシステム株式会社
技術計算部 シニアエンジニア兼係長 八尾 英成様(左)
社長 仁衡 琢磨様(中)
システムマネジメントサービス部 係長 古関 剛史様(右)
情報セキュリティのプロがいる安心感──経営者と登録セキスペが語る現場のリアル
経営者の視点から見た資格者の価値、現場での実践的な活用、そして社員の成長を支える社内制度まで。
資格取得を通じて広がる可能性と、企業文化として根付く情報セキュリティ意識について、仁衡社長と登録セキスペの八尾様・古関様に語っていただきました。
経営者へのインタビュー
Q 登録セキスペ資格保持者がいることで経営者の視点で何かメリットはありますか?

仁衡社長:はい。メリットがあります。
弊社はオーダーメイドのソフトウェア開発を行っており、国立研究開発法人や大学の研究者からの案件を多く受注しています。入札の仕様要件に「登録セキスペ」が含まれることもあり、当社には登録セキスペが2名在籍しているため、こうした業務に参加できる資格があることは非常にありがたいと感じています。公的な研究機関であると研究成果のデータ自体、第三者に盗まれることはあってはならないことになりますので、セキュリティ担保の要求も当たり前となってきています。
Q:登録セキスペの方がいることは、情報セキュリティの分野に関して社内の従業員のスキルや業務の質のレベルアップに役に立ちますか?
仁衡社長:はい。役に立っています。
当社は資格取得報奨金制度を長年継続していまして、資格を取った人がいるときは、全社会議で報奨金をお渡しする儀式をずっと行っています。社員の間でも、「当社には登録セキスペが2名もいる」という認識が広まり、セキュリティに対する意識が非常に高まっています。
二人の担当外の案件でも、情報セキュリティ上心配なことが起きたとか、何か課題が出たという時に、八尾や古関に相談することができるというのは、大きなことかと思います。
Q 資格更新の維持のための費用を会社がご負担されている背景にはどのようなお考えがありますか?
仁衡社長:毎年、講習を受けて情報セキュリティのスキルのアップデートできるのが登録セキスペの良い点だと思っています。
重要な知識や新しい情報を講習によって取得できているので、他の資格との違いをすごく感じています。
例えば、お客様から「最近ニュースでサイバーセキュリティの被害が増えていると聞いたが、うちのシステムは大丈夫か?」といった相談を受けた際にも、2名の登録セキスペが講習で得た知識を活かして的確に対応し、お客様に安心感を提供しています。資格の更新に必要な講習の受講費用を会社が全額負担することにしているのは、二人の活躍を今後も継続して期待し、今までの成果も認識しているからです。
登録セキスペの方々へのインタビュー
Q 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の資格を知ったきっかけや、登録を決めた理由について教えてください。
八尾様:前身の情報セキュリティスペシャリスト試験に合格していたところに、情報処理安全確保支援士制度が開始されるということで、登録を考えました。ただ、更新するための講習費用がそれなりにかかり、自己投資としては費用負担の割に活用の機会が少なく登録を迷いましたが、会社に相談したところ、費用を支援してもらえることとなり、また、業務として資格を活かす機会が増えるということも考えて登録を決めました。
古関様:情報処理技術者試験を受験する中で、高レベルの試験を受験しようと考えている時期に、情報処理安全確保支援士が創設され、会社から資格取得や登録を支援されていたこと、支援士登録による資格の裏付けが強まったことから登録を決めました。試験では情報セキュリティの一般知識以外にもプログラミング、ネットワークといった幅広い知識が求められ、自分の専門外のの分野の学習には苦労しました。
Q 登録セキスペの資格を取得されたことで、どのような意義やメリットを感じていらっしゃいますか?
八尾様:登録セキスペだけでなく他の資格にもいえることですが、資格によって客観的な裏付けと自信を与えてくれるという点に意義があると考えています。
業務で顧客のシステム管理を担当しており、顧客からセキュリティに関する相談を受けることもあるのですが、そういったときに、自分としては支援士として責任を持って回答することを心がけますし、相手には安心して相談してもらえていると思います。
古関様:名刺に支援士のロゴを掲載させていただいているのですが、お客様に名刺を出した時に「ええ!情報安全確保支援士を持っているのですね」というようなことで信頼を得やすい。やはりセキュリティ関係とかは今、すごくお客様も意識が高いのかなとは感じています。
Q この資格をどのように活用していますか?これから先、どんな場面で使っていきたいと思っていますか?

八尾様:私は担当業務として、顧客向けのアプリケーションシステム開発に加えて、お客様のシステム運用のサポートとして、新しく設置するサーバーの設定、ソフトウェアのインストール、セキュリティアップデートなどを行っています。
新しいツールの導入や脆弱性情報への対応などの顧客からの相談に対して、なるべく最新の脅威動向を踏まえたセキュリティ対策を提案するなど、知識を具体的な形で役立てることを意識しています。長年お客様と良好な関係を維持しているので、これからも安心してシステムを使ってもらえるように、支援士として、適切な助言や手助けができればよいと考えています。
古関様:社内の情報セキュリティ強化に活用しています。また、現在、オンプレミスからクラウド環境へのシステム移行に携わっているため、支援士として、より専門的な立場で力を発揮したいです。
Q オンライン講習を受講して、新しい学びや、スキルアップにつながる内容はございましたか?
八尾様:技術的なことは比較的自分でも情報収集したりはするのですが、制度や法令、マネージメントやインシデント対応などは自分から学ぶ機会が少ないため、そういったところを毎年のオンライン講習で補っています。
また、毎年、自分が支援士であるということを自覚し直す良い機会にもなっています。
古関様:年に1度、オンライン講習を受講することで、新しい知識や情報を得ることができました。また、これまで漠然として得ていた知識や情報を整理することができ、有意義な機会となっています。今年はAIに関しての情報が掲載されていて、自分の漠然とした知識を体系化して学ぶことができたと感じています。
Q 実践講習を受講して、業務に活かしてみたいことがあれば教えてください。

八尾様:これまでの実践講習の内容は現状の私の業務とは少し領域が異なり、受講した内容を直接活かせるところは少ないのですが、常にセキュリティ面も考えるという思考は活かしていきたいと思います。今後、民間事業者等が行う実践講習などで、業務に直接活かせるような講習を受講したいと考えています。
古関様:インシデント対応では、さまざまなステークホルダーによる視点が重要であり、その中で支援士が俯瞰してインシデントに対応していくことの重要性を学びました。私は、社内システムの基盤も担当していて、ルータや無線LANなど、古い機器や、古い規格で使っていた無線LANなどを交換してセキュリティ改善してもらったりもします。また、社内全体としてベースを上げていくプラス・セキュリティ人材の強化の活動もしています。
Q これから資格を取ろうと思っている方へのメッセージをお願いします。
八尾様:業務やそれ以外においても、日々、情報セキュリティの必要性が高まっていると実感しています。そのような状況で、一人の支援士として仲間が増えるのはとても心強いです。皆さんの資格への挑戦と、支援士としての活躍を応援しています。
古関様:情報処理技術者試験を通して、幅広い知識や、より専門的な知識を学ぶことができました。支援士登録後もオンライン講習による知識のアップデートや、実践講習によるスキルアップを図ることができます。実践講習で受講できる講習が年々増えており、今後が楽しみな資格です。