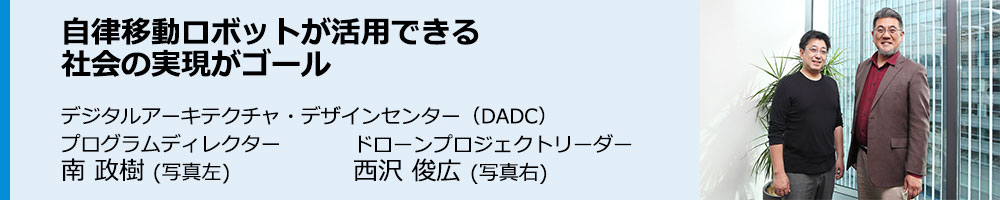アーカイブ

自律移動ロボットワーキンググループ インタビュー
公開日:2021年4月7日
デジタルアーキテクチャ・デザインセンター
全体像の課題を洗い出し、 ドローン産業の見取り図を作る
取り組んでいるテーマや目標は?
南

2050年頃、日本の生産年齢人口は5,000万人くらいになると言われています。現在が7,000万人ですから、生産年齢人口が減っていく中で、どのように社会を維持していくのかという課題があります。そこで、足りなくなる労働力を補うための一つのキーポイントとなるのが自律移動ロボットです。各企業が自律移動ロボットを開発してこの課題を解決していく方法もあるのですが、バラバラにやっていくと大資本を持つ企業の独壇場になってしまうなどの懸念が生じます。
Society5.0が示す「社会はどうあるべきか」「何が必要になるか」のように全体像を俯瞰して、現状の政策や法律、研究開発支援などを見直し、改革を進めていかなければ、日本はどんどん世界から遅れていってしまうでしょう。その解決を考えるための全体像を描き、その見取り図を作ることが、「自律移動ロボット」ワーキンググループのテーマです。
西沢
私たちのグループでは、特にドローンを大きなテーマとして取り扱っています。ドローンが物流や点検、警備などさまざまな分野に活用され、2030年以降に空を見上げたら、ドローンが10機くらい飛んでいる世界を実現することが目標です。その際の課題となるのが、ドローンの飛行におけるルールや、落下した場合の補償制度などの整備です。あらゆる状況を網羅した全体の仕組みがなければ、ドローンは空を飛べません。それを解決するための産業アーキテクチャ設計をしっかり考えていくことも、私たちの大事なミッションです。
役割を分担して、 暗中模索しながら 産業アーキテクチャ設計を進行
具体的な活動内容は?
南
私は本プログラムディレクターとして、全体の統括をはじめ、関係省庁とのリエゾンや外部でのレクチャーなどの渉外を担当しています。もともとドローンの研究者でしたので、産業アーキテクチャ設計ではドメインエキスパートとして参加しています。
アーキテクトの方々と議論していると、ドローンの研究者だった私が、今まであまり意識してこなかった法律や産業とドローンに繋がりがあることを初めて知ることがあります。この新たな知識をどのように産業アーキテクチャ設計に反映させていくのか、試行錯誤していくプロセスが面白いと感じています。
西沢
具体的にどのような産業アーキテクチャを設計していくのかといったことを、リードして進めていくのが私の役目です。現在、ステークホルダーの方々にドローン産業を振興していくための課題やニーズなどを伺うヒアリングを進めていますが、ドローンの産業利用が国内で本格化していないため、さまざまな課題を抱えていることを実感しています。
出向元の企業では複数の研究開発や製品開発のプロジェクトをリードした経験があり、手法は大体決まっています。ところが、産業アーキテクチャを設計すること自体、今まで誰も経験がありませんから、課題をどのように解決していくのか、暗中模索しながら進めているのが実情です。
企業の視野を越えた高い視座で、 全体最適なガバナンスづくりに挑める
DADCで活動できる醍醐味や魅力は?
西沢

一企業にいると、自分たちの事業を起こすとか、利益を上げることが主になり、どうしても視野が狭まります。それに対して、DADCでは産業界の声を落とし込んで全体を取りまとめ、各省庁も巻き込んで共に作り上げていくことができます。企業が自分たちの利益を上げるためのルールづくりをするのとは全く異なり、国全体に最適なルールやガバナンスを作ることができるのが、DADCならではの醍醐味です。ここで学ぶ貴重な経験は、将来、出向元に戻った際、高い視座に立った観点で新事業を起こすような場面で活かせると思っています。
南
公半民的な組織の中で、民の心を持ちながらグローバルな視座で、日本の勝ち筋を見つけ出し、国の産業を立ち上げるような仕事ができる機会は、なかなかありません。また、デジタル庁が誕生するなど、政府が世の中はこれからデジタルに移行していくという大号令を発している中で、日本の産業を今以上に進化させていく仕事に、多くの時間と労力を使ってやり遂げていくのは希少なチャンスです。それが、DADCで活動できる面白さです。
産業アーキテクチャ設計では、さまざまなステークホルダーとの連携が欠かせません。その中で築かれていく人のネットワークも大きな魅力です。特に、ベンチャー企業の方々は、今だからこそビジネスモデルにできると、ドローンの産業利用実現に命がけで取り組んでいます。その熱量に触れるたび、新たな時代の産業や社会を創造する人々を目の当たりにした気持ちになり、自身のモチベーションも上がります。
世界と戦える産業アーキテクチャを設計し、 コミュニティベースで社会に実装
今後、取り組んでいきたいことは?
西沢
産業アーキテクチャを設計するだけではなく、社会に実装していくのが私たちの最終ゴールですが、その中で重視しているのは、日本をガラパゴス化しないことです。国内だけに通用する産業アーキテクチャを設計しても意味がありません。海外の企業に先を越されて、日本のドローン産業が吞み込まれていかないよう、世界としっかり戦えるような産業アーキテクチャを設計していきたいと考えています。
南
コミュニティ形成に関心があり、すでに取り掛かっているところです。例えば、インターネットサービスを運用しているオペレーターの方たちは、企業の垣根を越えて大きなコミュニティを形成しています。東日本大震災が発生した時、通信ケーブルが切断されたのですが、このコミュニティを通じて協力し合い、迅速に復旧作業に着手できました。それは、非常時で危機感があったことに加え、コミュニティ内に信頼関係が構築されていたからこそだと思います。よく「社会的受容性」と言いますが、それがないと世の中に普及しませんし、経済合理性も成り立ちません。
産業アーキテクチャ設計は、社会的受容性と経済合理性の両輪が不可欠です。今後、現場で実際にドローン産業を支えていく人々がしっかり繋がれるコミュニティを作り、そこを起点に社会実装を進めていきたいです。DADCなら、それが実現できるのではないでしょうか。
更新履歴
-
2021年4月7日
自律移動ロボットワーキンググループのメンバー・インタビューを公開しました。