
2024年12月14日、「量子コンピューティング技術シンポジウム2024」を開催しました。今年度のテーマは「量子人材育成の最前線」。量子技術の産業化に向けて、量子人材育成の重要性はますます高まっています。現在、多くの組織が量子人材育成を実施しています。経験のない初学者から専門家まで、さまざまなレベルの興味・関心が存在しますが、これらの組織では多様な育成プログラムを提供し、学習ニーズに応えるよう取り組んでいます。本シンポジウムでは、学習の機会を広く共有し量子人材育成の現状を確認するとともに、実用化・産業化の時代に向けて、より効果的な人材育成を進めるために目指すべき未来を展望しました。
開会挨拶
シンポジウム開催にあたり、西村 秀隆 氏(経済産業省 大臣官房 サイバーセキュリティ・情報化審議官)よりビデオレターで開会挨拶が寄せられました。国による量子人材育成の取り組みとして、未踏事業および量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)が紹介され、各組織との協力体制の連携の強化のもと、量子技術の研究開発・産業化の推進によって、国際競争力をリードする人材の輩出が進むことへの期待が述べられました。
基調講演「量子コンピュータ人材エコシステム:教育・研究・産業の連携」
続いて藤井啓祐氏による基調講演が行われました。藤井氏は大阪大学大学院基礎工学研究科教授、QIQB副センター長であり、未踏ターゲット事業のプロジェクトマネージャーを務めています。ほかに株式会社QunaSys創業メンバー・最高技術顧問を担うなど、産学連携も含めて幅広く活躍する立場から、量子コンピュータ人材についての現状と今後の展望が語られました。

藤井 啓祐 氏(大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授/QIQB 副センター長)
「量子コンピュータのハードウェアは順調かつ着実に進化してきました。2023年には理化学研究所(理研)、産業技術総合研究所、情報通信研究機構、大阪大学、富士通株式会社、日本電信電話株式会社の共同で、初の国産超伝導量子コンピュータが開発されました。これからは、基礎研究人材だけでなく、開発やビジネスを行える「量子+α」の人材がますます重要になってきます。
このような現状のなか、未踏ターゲット事業の修了生が国産量子コンピュータの進化や普及に大きな貢献をしています。
大阪大学量子ソフトウェア拠点の取り組みとしては、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)COI-NEXTに採択された量子ソフトウェア研究拠点があります。量子コンピュータソフトウェア開発のエコシステムをボトムアップで醸成していくことを目的としており、企業34社と6機関(2024年11月現在)が参加しています。また、社会実装のためにスタートアップQuELの立ち上げも行い、大学発ベンチャー表彰などを受賞しています。ほかに、全国の企業人や学生を対象にした量子ソフトウェア勉強会の実施や、量子関連企業のジョブマッチングイベントとして量子コンピュータジョブフェスタを開催しています。
今後、持続可能な人材育成が競争力においてより重要になるでしょう。先入観のない若年層から「量子」を身近なものとして感じてもらうことが重要です。AIがかつてそうだったように、「量子は難しい…」と避けて通れない時代になりつつあります」
量子人材育成事例
量子人材育成に取り組む企業や研究機構から、人材育成の事例紹介が行われました。
基礎から学べる量子人材育成プログラム「Q-Quest」
1つ目の事例紹介はJellyWare株式会社の稲垣 尚起 氏から、「量子の世界の扉となる!量子人材育成プログラム「Q-Quest」の取り組み」と題し、同社が実施する量子人材育成プログラムが紹介されました。

稲垣 尚起 氏(JellyWare株式会社 チーフビジネスデザイナー)
「JellyWareが提供するQ-Questは、オンラインで学べる無料の量子コンピューティング学習プログラムです。文部科学省の事業として、量子技術を理解・活用できるリテラシーを有した人材を育成することを目的としています。初めに学ぶ基礎学習プログラムは、基礎的内容を学び、量子技術のリテラシーを身につけることを目的としています。ジェネラリスト向けとエンジニア向けがあり、プログラム内容が異なっています。次に受講する事業創造プログラムでは、チームを組み、ビジネス性があり実際に動くプロトタイプを作成することをゴールとしています。チーム活動をしながらアウトプットを出すことを重要視し、ハンズオンの実施やチーム組成のサポート、伴走支援などを整えています。最後にDEMO DAYでピッチを行い、企業や投資家、量子技術に関心のある人材と交流し、ビジネスにつなげていきます。昨年度のDEMO DAYでは航空ルート検索の新たなサービスや製薬企業・創薬ベンチャーのR&Dパイプラインの将来価値を評価し、価値最大化をするためのR&D計画を最適化計算に基づいて提案するサービスなどが発表されました。今後もQ-Questを量子業界の入り口の“扉”となるための取り組みにしていきたいと考えています」
NICTが実施する量子ICT分野人材育成プログラム「NQC」
次に、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が実施する量子ICT分野人材育成プログラム「NQC」について、同機構量子ICT協創センター 主任研究員の横山 輝明 氏から説明が行われました。
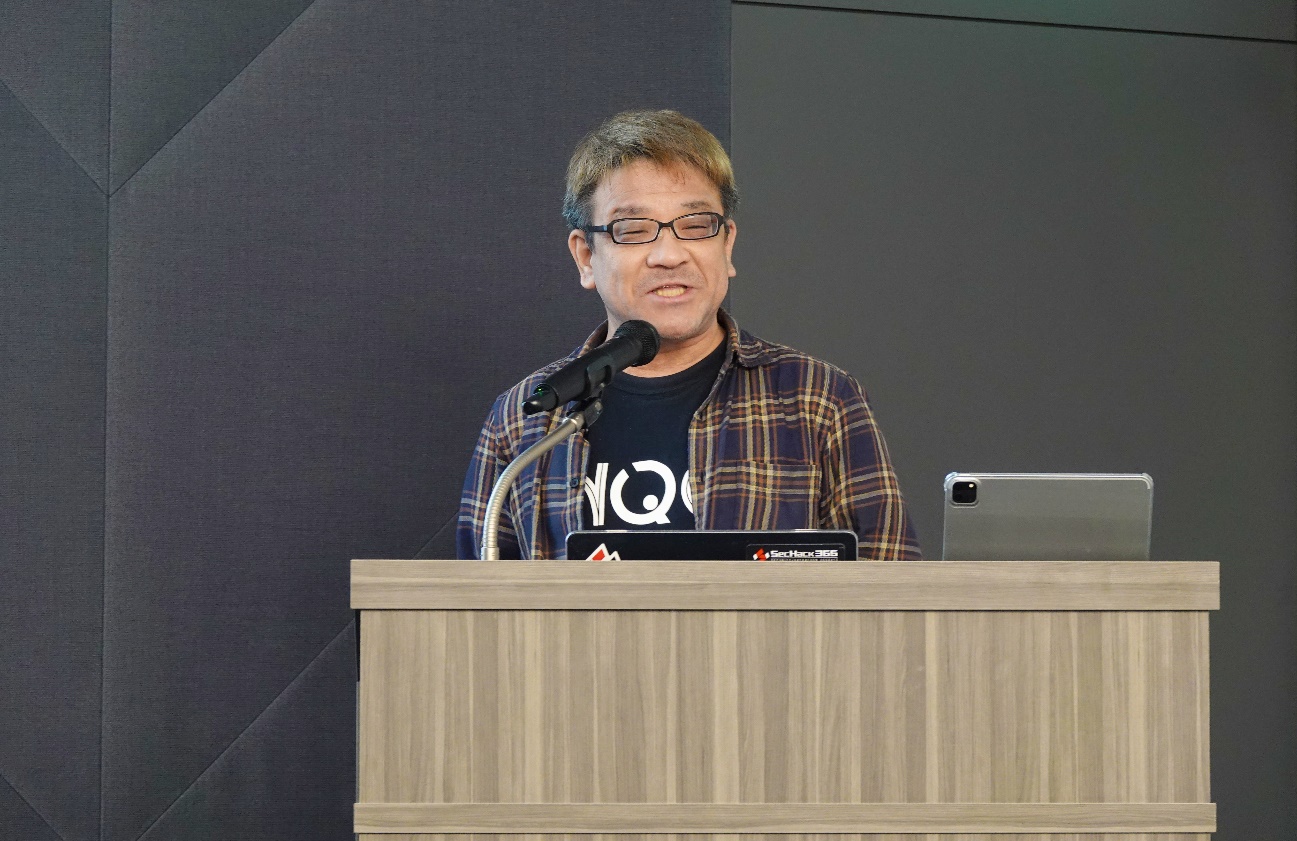
横山 輝明 氏(国立研究開発法人情報通信研究機構 量子ICT協創センター 主任研究員)
「国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が行っている量子ICT分野の人材育成プログラムがNQCです。2020年度から、大学や企業等と連絡し、年齢制限は設けずに、高専生や大学生、修士・博士課程在学者等を対象として、量子ICTに関する講習会等を実施するプログラムを行っています。一般向けの公開セミナー、半年程度の体験型の中長期型のプログラム、さらに研究開発のテーマを持ち込んでもらって支援する探索型の3階建てになっています。多様な参加者をハードル低く受け入れることを意識しており、女性の参加者や高校生、社会人の参加例もあります。修了後はサポーターとして手助けをしてもらう制度もあり、継続して関わってもらうことでコミュニティが形成されることも目指しています。講義だけではなく、参加者同士の交流機会も提供。IBMや理研の見学会も実施しました。
受講者の皆さんには、このプログラムをステップに、量子の世界に進んでいただきたいと思っています。我々NICTでも働けるポジションを用意しています。育成の場を作り、還流の場を作り、その中にNICTも位置することができればと考えています。
すそ野が開けていることはもちろん大事ですが、足を踏み入れた後に食べていけるのか、豊かな中腹が見えていることが大切です。我々は多くの人を巻き込むことに汗をかき、量子周辺で滞留してもらえるようにしたいと思っています」
量子コンピュータスタートアップ企業から見た量子人材の育成
続いて、量子コンピュータのスタートアップ企業株式会社QunaSysのCOOを務める松岡 智代 氏から「産業における量子人材の活躍に向けて」と題した講演が行われました。

松岡 智代 氏(株式会社QunaSys COO)
「株式会社QunaSysは量子コンピュータソフトウェアとアルゴリズムのスタートアップです。58名の社員のうち36名が技術者で、5年間で論文45件発表するなど技術開発に軸足を置いている会社です。材料開発領域での量子アルゴリズムの共同研究開発、CAEなど新規応用領域の共同研究開発が現在の主な事業です。
量子人材育成の取り組みとしては、エンドユーザー向けの教育アプリQURIの提供、量子コンピュータ活用のコミュニティQPARCの運営、量子アルゴリズム性能評価指標の標準化を行うQAGCの運営などを行っています。
量子という新しい産業をたちあげていくためには、産業の課題に量子をつなげていく人材の育成が不可欠です。課題と感じているのは、関わる人の価値観の違いが大きいということです。量子コンピュータをビジネスで使っていこうとすると、理論分野だけでなく、様々な範囲にわたる技術が必要となり、営業など技術者以外の人材も含めると非常に多様な人材が必要になります。また、もともと量子分野以外を専門とする人に、量子分野にとどまってもらうためには魅力を伝えていく必要があると感じています。
ビジネスとして量子コンピュータをやっていく中で起きがちな問題として、顧客が求める満足度と研究者として追求したいアカデミック成果が一致しないということがあります。双方が満足できるようにするためには、高い専門性と顧客事業の理解、技術的構想力とプロマネ力が必要です。技術的面白さを顧客価値につなげる力や不確実的なものをコミットする力が必要であり、成果と面白さのバランスを取ることが重要だと思っています」
NEDOが実施する量子懸賞金事業の取り組み
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の工藤 祥裕 氏より、同機構が新たな取り組みとして開始した量子懸賞金事業について紹介が行われました。

工藤 祥裕 氏(新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) AI・ロボット部 量子ユニット ユニット長)
「NEDOが実施する懸賞金活用プログラムは、通常の研究支援のスキームとは異なり、結果を評価する懸賞金事業となります。最終的に優れたユースケースを表彰し、優勝賞金として2,000万円以上、賞金総額2億円を用意しています。採択金ではなく、最終的に懸賞金が出る新たな取り組みであり、参加者の競争の場として位置付けたいと考えています。
量子懸賞金事業は、まず課題提案者から課題を募集します。領域設定としては、我が国の社会課題の解決や新産業の創出に資する領域を設定しています。優れた案を出した人に対しては最先端の開発環境を無料で提供します。それと同時にコンテスト参加者を募集します。コンテスト参加者は課題に対する解決案を提案します。コンテスト参加者には量子分野以外の技術者でも応募が可能です。教育プログラムを実施して、量子分野以外のドメイン知識を持つ専門家や、数学・物理・情報科学などの才能がある挑戦者に量子コンピュータについて学んでもらうことができます。もちろん元から量子コンピュータの研究に携わるエキスパートにも加わってもらい、自由な発想で研究に取り組んでもらうことが可能です。
近年、多くの組織が量子人材の育成に取り組み始め、実績を上げてきているなかで、それらの取り組みを連携していくことが重要になっています。産業化を見据えてチャレンジする場の重要性が増すなか、敷居を下げる工夫、いろいろな人が流入してもらえるようにする試みのひとつとして量子懸賞金事業を実施しています」
IPAが実施する「未踏ターゲット事業」における量子人材の育成
最後に、IPAが実施する量子人材育成の取り組みとして、独立行政法人情報処理推進機構の長澤 良次より未踏ターゲット事業量子コンピューティング技術分野の紹介が行われました。

長澤 良次(独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター)
「未踏事業は新しいITの世界を作り出す「突出したIT人材」を発掘・育成する事業です。応募者の提案をプロジェクトマネージャーや審査員が審査して採択者を決定し、育成を行います。3種類の未踏事業があり、未踏ターゲット事業は次世代ITを活用して世の中を抜本的に変えていけるような先進分野のIT人材を育成する事業です。そのなかのターゲット分野として量子コンピューティング技術が設けられています。採択されると、作業時間に応じて最大378万円が支給され、先進分野の専門家のプロジェクトマネージャーからサポートが受けられたり、知的財産はすべて採択者に帰属したり、開発環境が提供されたりするなどの特徴があります。
2018年から事業を実施してきましたが、さまざまな年齢層からの応募があり、学生と社会人のバランスも均衡するなど多様な層からの参加が実現しています。量子コンピューティング技術シンポジウムの開催をはじめ、量子人材のすそ野拡大に向けた取り組みも実施しています。
2025年度からは支援の時間単価を引き上げ、上限金額を396万円に増額します。開発環境の追加を予定しており、産業技術総合研究所 G-QuATと連携してゲート式量子コンピュータの実機の利用を検討しています。未踏ターゲット事業の公募期間は2025年3月6日までです。皆様のご応募をお待ちしております」
パネルディスカッション「量子時代を切り拓く人材育成の挑戦」
休憩をはさんで、「量子時代を切り拓く人材育成の挑戦」をテーマにパネルディスカッションが行われました。
パネリスト
門脇 正史 氏
産総研 G-QuAT / 株式会社デンソー AI研究部
高野 秀隆 氏
一般社団法人日本量子コンピューティング協会 代表理事/株式会社長大 事業戦略推進統轄部 クオンタム推進部 部長
松岡 智代 氏
株式会社QunaSys COO
モデレーター
嶋田 義皓 氏
科学コミュニケーター

左から嶋田氏、門脇氏、高野氏、松岡氏
量子人材育成の現在地:最新の取り組みと成果
嶋田氏「まず量子人材育成について、皆様の現状認識を教えてください」
門脇氏「私が所属するトヨタグループでは、ボトムアップとトップダウンの双方で量子人材育成の取り組みがあり、それぞれのメリット・デメリットが見えてきているところです。未踏事業では採択された計算力学分野の助教授が異分野から量子分野に入って成果を上げ、さらに元の専門分野でも量子を活用していこうという機運が高まったという例を見ていて、成果があったと感じています。いま、AIと量子コンピューティングが融合することで、科学研究の自動化に向けて進んでいます。そこに賭けてくれる人材が出てきてくれることに期待しています」
高野氏「IT企業創業の経験から、ビジネスを見据えて動くことを重要視しています。都市計画コンサルティングなどの経験を経て、街づくりに量子を活用する「クォンタムシティ構想」というビジョンを提唱し、研究開発、人材育成、データセンター事業、ベンチャー支援を展開しています。技術の活用を目的とするのでなく、ビジョンの実現に向けて動くことが大事です。ビジョンに共鳴した自治体とも現在連携に向けても動いているところで、収益化には巻き込み力が欠かせないと思います。量子人材の育成としては、2023年からは日本量子コンピューティング協会の理事に就任し、量子人材育成講座を開講して資格検定試験を実施しています」
松岡氏「先ほどの登壇のときに弊社の人材育成についてはお話ししましたが、現在量子の置かれているフェーズでは、お客様に対して量子であることの価値を理解してもらう必要があるので、一部の研究者がその理解を促す役割も担っています。しかし、本来ならば研究者は研究視点でやりたいことをやったほうがよいのではないか、と思っています。市場がもっと成熟すれば研究者は研究にフォーカスできるようになるのではないかと思います」
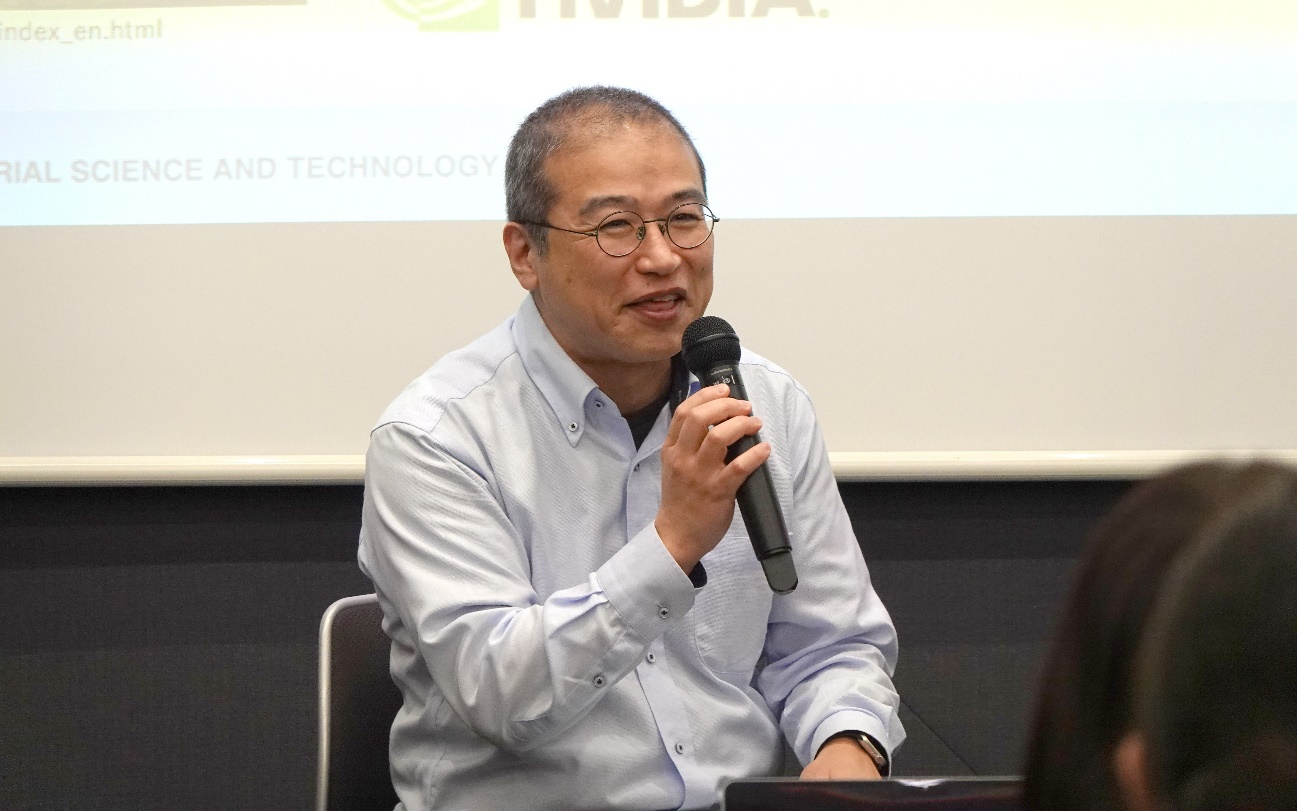
門脇 正史 氏(産総研 G-QuAT / 株式会社デンソー AI研究部)
量子人材育成の挑戦:直面する課題とその解決策
海外と比較した日本の状況は
嶋田氏「海外と比較したときに、日本の状況はどうでしょうか」
門脇氏「日本では、今のような状況を見越して、大学で量子の教育を充実させてこなかった、海外と比較すると弱いという先生もいます。層の厚みや卒業者の数を見ると、その事実はあると思います」
松岡氏「給与に関しては、海外では一般的に給与が高騰しているので、量子人材に限った話ではないと感じています。為替の問題もあり、そこを認識したうえで考えていく話だと思っています」
高野氏「日本以外はハードの開発に資金を投入している傾向が強くあります。日本ほど産業応用に積極的なところはなく、そこに勝ち筋があると思います。それが将来的に正しいかどうかわかりませんが、熱量を持って道標を示せる存在が必要ですし、不足していると思っています。産業界と量子技術者の接点が少ないとも感じています。そこで私たちは人材のマッチングも始めています。量子人材本人は、キャリアアップが可能だというイメージを持ってほしいと思います」
門脇氏「コミケに行きたいから日本でポスドクをやっているという外国人もいるように、オタクにとっては代えがたい価値が日本にあるので、そこを恥ずかしがらずに全面に出すとよいのでは。また、会社の人事制度として、総合職しかないので、専門職制度が必要だということを政府レベルで言ってもらいたいと思います。特別なスーパースターを1人呼べば周りのレベルも上がるので、そういう人を呼ぶためにも企業で専門職と総合職を分けた会社が増えることが望ましいと思います」
松岡氏「海外の量子のエコシステムにはほぼベンダーしかいません。ユーザー企業やアプリケーション側がこれだけ多いのは日本の特徴です。日本らしい特徴を打ち出せれば海外からももっと興味をもってもらえるのではないかと思います」

高野 秀隆 氏(一般社団法人日本量子コンピューティング協会 代表理事/株式会社長大 事業戦略推進統轄部 クオンタム推進部 部長)
社内で量子人材確保を行うことはできるのか
嶋田氏「オンラインから質問が来ています。会社で『量子をやれ』と言われるが人材がいません。この課題に対してはいかがでしょうか」
高野氏「日本量子コンピューティング協会では、資格認定者を獲得したいという企業に人材を紹介するという支援ビジネスの実施を始めました」
松岡氏「量子人材もいろいろあります。企業の方にはFTQCをすべて理解しているといった専門的な知識は必要ではありませんが、我々のような専門家集団をマネージするための知識は必要です。そういう人材を育成するプランを活用するとよいと思います」
門脇氏「社内を探すと、能力のある人がいる可能性があると思います。物理学科出身の人は、もう一度物理をやらないかと誘ってみると、かなりの確率でやってくれますし、能力もあります。きっと御社のなかにもいると思いますので、社内公募してみるのもひとつの手です」
量子分野に留まってもらうには
嶋田氏「量子コンピューティングの研究をしているM2の院生の方から、今後の見通しがたたない量子にとどまる勇気がないというお悩みが寄せられています」
高野氏「検定ビジネスなどをやりながら、人材育成に隠れている課題感を集約して、提案書を国に提言する準備を進めています。それによっていろいろ変えることができるのではないかと考えています。なのでもう少し待って、踏みとどまってください」
門脇氏「量子に関して学んだことは無駄にならないし、情熱をもって学べれば、ほかの技術領域というのも絶対上がってくるので、まずは量子でがんばってみてほしいです。そのがんばりがあればどこへ行っても大丈夫です」
松岡氏「それは営業部門でも同じで、量子コンピュータのソリューションが売れたらこの後どんな営業でもできる、と社内でも話していたところです(笑)。技術が不確実でアプリケーションが見えていないものを売るにはきちんとした説得をしなければいけないですし、道筋も示さなければいけない。全部の能力が身につくんですよね。技術の方も同様に、難しい状況のなかでがんばることができれば、どんな領域でもがんばれるのではないかと思います」

松岡 智代 氏(株式会社QunaSys COO)
量子人材育成の未来図:展望とマイルストーン
嶋田氏「最後にこれからの量子人材に関する展望をお聞きします」
松岡氏「弊社の事業部それぞれに合わせた人材像を設定して人材育成を行っていきます。次世代の産業アプリケーションに貢献する新たなアルゴリズムを生み出していくリサーチでは、技術を生み出す初めの1歩を踏み出せる人材を獲得する必要があります。Quantumソリューションはハードウェアの開発者やアルゴリズムの開発者がFTQCに向けて開発を効率的に行えるソリューションを提供するため、量子を理解しつつ開発者が使いやすいようにSDKなどとして提供するエンジニアリングができる人材育成を考えています。ケミカルリサーチソリューションは、量子コンピュータを化学領域の産業で本格的に使うソリューションを生み出す部門なので、化学分野をきちんと理解し、量子コンピュータとつなげられる人材を育成することが必要と考えています」
高野氏「私たちが実施する量子人材資格認定制度によって、年間1,000人、3年以内に3,000から5,000人の資格認定者を生み出します。そして、その中から突出した“金の卵”を見つけます。仮に金の卵が20人見つかり、それぞれ50万人のエンドユーザーを抱えるようなアプリケーションを生み出すことができれば、内閣府の『量子未来社会ビジョン』が打ち出した、“2030年に1,000万人のエンドユーザー”に到達します。この数字について、何年内にどうするという具体的な数字を出しているのを私は他で聞いたことがありませんが、ビジネスマンとしてしっかりやっていきたいと思っています」
門脇氏「私のビジョンは、『量子とAIが科学と学問と、エンジニアリング・社会実装を支える』ということをみんなで考えていく、そのための活動をするということです。会社から産総研に出向している身としては、会社にとって量子がどう使えるのかを見出していくのが自分のミッションだと思っています。大きな目で見ると、エンジニアリングのソフトウェア部分は特定の大企業が担っているので、それらの会社が採用したくなるような新しい概念を作っていくことが大事だと感じます。量子インスパイアドという言い方が適当かはわかりませんが、量子でできることを研究する傍ら、GPUでも実行できるアニーリングの技術などがCAEにどう役に立つのかを研究し、まずこちらから実装していこうと考えています」

嶋田 義皓 氏(科学コミュニケーター)
閉会挨拶
最後に下出 政樹(独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター イノベーション部長)から閉会挨拶が述べられました。量子技術への期待が高まり実用化の流れが加速する中、人材育成の重要性がますます増していることを踏まえ、未踏ターゲット事業による人材育成に加え、今後も量子技術に関わる機関との協力関係を推し進め、共に量子業界を盛り立てていく決意が述べられました。


