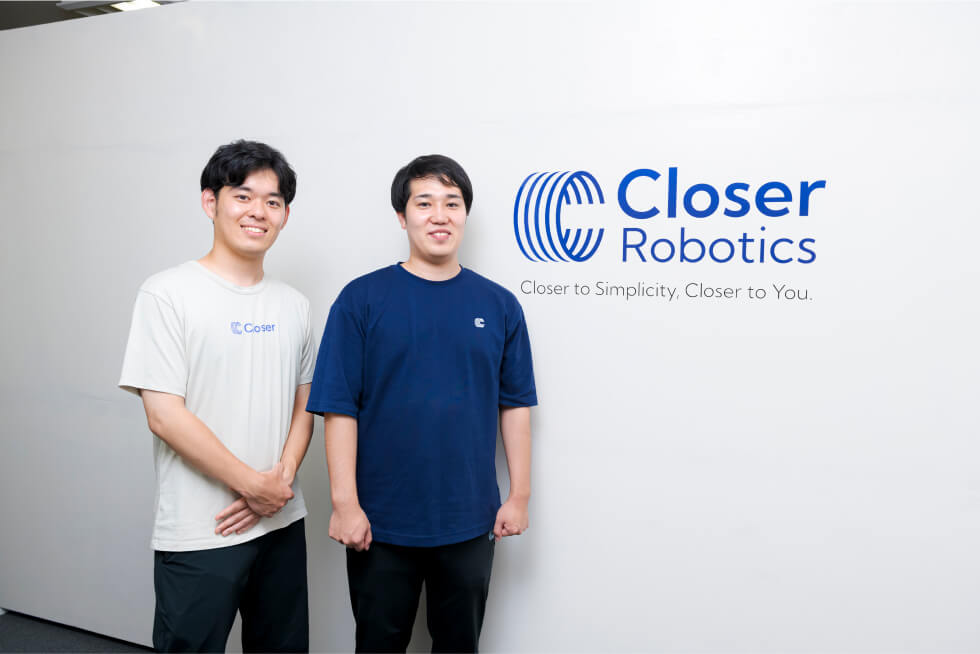
未踏に応募して採択されると、どんな世界が待っているのか? 応募するにあたっては、どのような思いがあったのか。実際に未踏を修了した方々に聞いてみました。
今回は、2022年度に「少量多品種の包装箱詰め作業を省人化するロボットシステムの開発」で未踏アドバンスト事業に採択され、食品製造業の包装工程で利用できるソフトウェアベースの小型のロボットシステムを開発した、樋口翔太さん、山根広暉さん、岡村柾紀さん、小熊一矢さんのプロジェクトについて、樋口さんと小熊さんに話を伺いました。

人材不足が深刻化する中で、自動車、電機、電子、金属などの製造業ではロボットの導入が広がっている。しかし、食品、医薬品、化粧品などの小規模な工場では既存の大掛かりなロボットシステムの導入は難しく、未だ普及にはほど遠い現状がある。現状の製造ラインに導入するためには、小型の汎用ロボットを使った小規模なシステムが必要だ。今回の未踏アドバンストのプロジェクトでは、食品製造業の包装箱詰め作業をターゲットにパラメータ設定を変更することで、様々なニーズに対応できるソフトウェアベースのロボットシステムを開発した。
人手不足を解消する現場に導入しやすい小型ロボットを
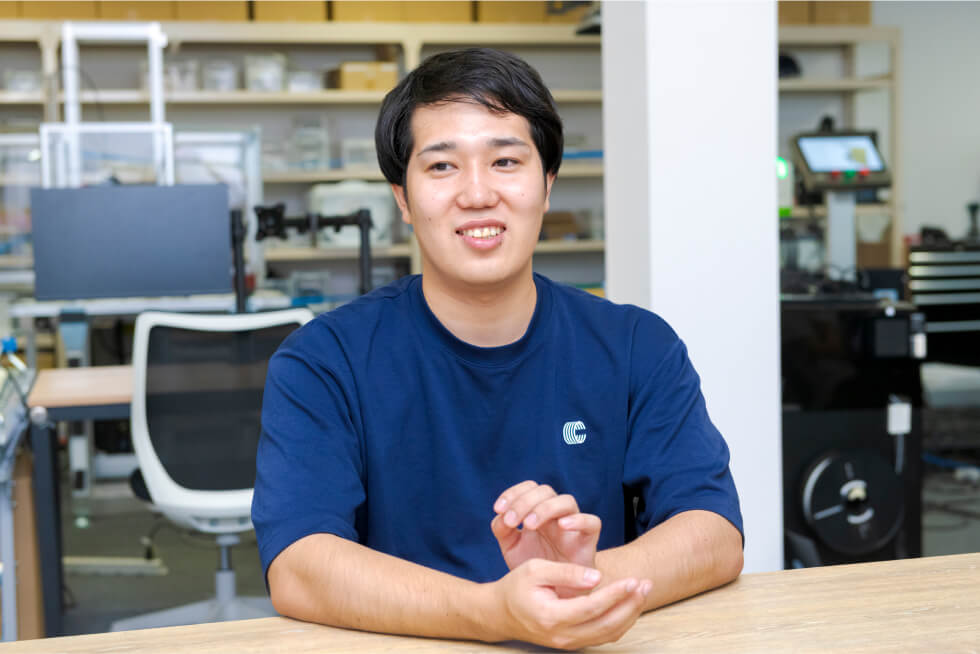
小規模工場向けのロボットシステムの開発を目指したのはなぜなのでしょうか。

子供の頃からロボット開発が好きで自律型ロボットのサッカー大会である「ロボカップ」に参加して、世界大会で優勝した経験もあります。高専時代はトマトを自動収穫するロボットの研究からより汎用的な農業ロボットの開発に取り組み、卒業後は筑波大学の大学院に進学して研究を続けていました。
農業分野でロボットを実用化するには時間がかかりそうだと感じていたときに注目したのが食品業界です。つくば市と共同で農業でのロボットのPoCをしていたときに、食品業界の方に誘われて工場見学に行って衝撃を受けました。ある程度自動化されていると想像していたのですが、ロボットは全く導入されていなくて、たくさんの人が働いていたのです。
食品業界や医薬品、化粧品などの“三品産業”は小規模な工場が多く、生産ラインからロボットまでをオリジナルで開発する大規模なロボットシステムの導入が難しいことを知りました。
小規模な工場で手軽に導入できる汎用的なロボットパッケージを開発したいと考えて、2021年にCloserを起業しました。長岡高専の後輩でやはりロボットを研究していた小熊も卒業してCloserに合流してくれました。

私は当初技術的に明るくなかったので、2年ほど外から見ていた感じですが、ちょうど修士課程に進学して本格的にCloserに合流したタイミングで、未踏アドバンストの話が持ち上がったのです。
未踏アドバンスト事業へ応募するきっかけは何だったのでしょうか。どんなことを期待していましたか。

チームメンバーの山根と岡村とは一緒にロボカフェを運営していたのですが、岡村は落合陽一さん(現・未踏IT人材発掘・育成事業プロジェクトマネージャー)の研究室に所属していて、未踏に関しては詳しかったんです。未踏修了生にはアカデミアの世界をリードしたり、有名なベンチャー企業を起業したりしているレジェンドが沢山いたので、参加してみたい、コミュニティに加わりたいとは思っていました。
ある日、メンバーとラーメン屋さんでみんなと話しているときに、未踏アドバンストに応募しようと話を出すと、全員が乗り気だったので応募することにしました。当時はCloserでプロトタイプを作って、展示会に出展したこともあって、開発のための資金をもらって完成レベルを高め、導入実績作りをしていくためにも、良いタイミングかなと思いました。

プロトタイプはある程度は動いたのですが、まだまだ課題がありました。未踏アドバンストでそれらの課題を解決できるのではという期待もありました。

技術的なところにフォーカスしたプロジェクト支援は他にあまりありませんし、私たちメンバーが根っからのエンジニアばかりだったので、ビジネスアドバイザー(BA)にビジネスに精通したすごい人たちがいるのも魅力でした。

ビジネスと技術の両方の知見を持っているロボット系のプロジェクトマネージャー(PM)もいて、プロの視点からアドバイスがもらえるという期待も大きかったですね。
人の作業をロボットに置き換えるというコンセプトを貫く
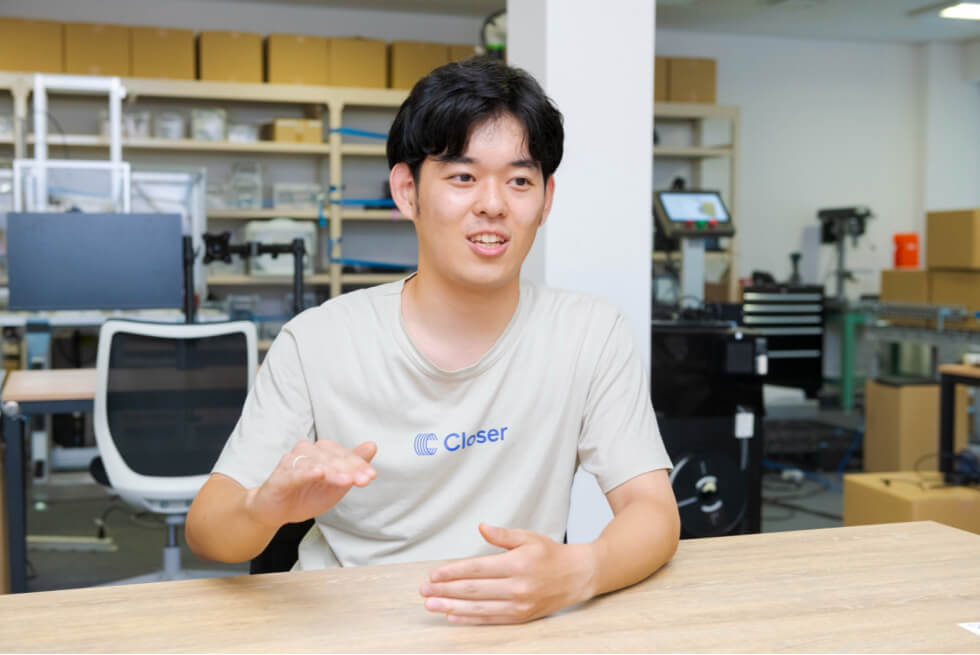
未踏アドバンストの期間中はどのようにプロジェクトを進めていったのでしょうか。

私たちが採択された年はちょうどコロナ禍でしたが、キックオフ会議や中間報告会、成果報告会までマイルストーンとなるようなイベントはハイブリッドで開催されました。

平野PMとは月1回のペースでミーティングをしました。オフラインで行われることもたまにありました。開発の進捗状況の報告をして、適宜アドバイスをいただきました。

特に画像処理系のアドバイスを数多くいただきました。ピックアップする対象物の認識の精度を上げる方法や、つかんで綺麗に並べるための画像の向きを捉える手法などを教えていただきました。
ただ、コロナ禍だったので、他の年度の人から聞いたような、未踏修了生の方たちと食事に行ったりする機会はなかったのが残念です。同じPMの他のチームの人たちとご飯に行ったりはしていましたが。
壁にぶつかったこともあったのでしょうか。

2022年度の未踏アドバンストのプロジェクトとしては成果を上げることができましたが、ビジネスターゲットの絞り込みが甘かったために、対応しなければならない動作が幅広くなってしまったことは少し反省しています。
開発資金が限られているときは絞って取り組むしかありませんが、開発資金の支援が得られる未踏のプロジェクトということで、多少スコープを広げて自由にやろうと考えてしまったことが裏目に出た感じです。

個人的には大学院の研究があって、しかも期間中にロボットの大会にも参加していたので、とにかく時間がなくて大変でしたが、人の代わりにロボットが動作するというコンセプトのものを一通りやりました。
技術的にはどんな難しさがあったのでしょうか。

例えば、包装されている小さな袋を取り上げて、特定の場所に置いていくという動作でも、どんな現場で使うのかによってスピードが変わってきてしまうので、処理パターンが増えてしまいました。

仮説として、取るところと置くところを分類していたのですが、全てに対応できる汎用的なものにしたために、開発に苦労しました。

一定の場所に対象物を置けば、あとはロボットが自動で処理することを、カメラだけで完結しようとトライアンドエラーしながら進めていきました。
会社としての開発力を身につけて次のステージに進めた

重い段ボールのパレットへの積載を自動化する小型協働パレタイズロボット「Palletizy」

Closerのオフィスの様子
未踏アドバンストに参加してどんなことが得られたのでしょうか。

今のCloserがあるのは、まさに未踏アドバンストがあったからだと思います。未踏での活動を通してCloserとして方向性が決まってきて、プロジェクトでの経験が目指すものに近づいていくためのブースターの役割を果たしてくれています。
今Closerでは小熊がフルタイムで働いていますが、他の二人のメンバーもパートタイムで一緒にやっています。ターゲットを絞って別のロボットを作る際にも、メンバー全員で未踏アドバンストでの経験を活かして方向性を固めることができています。

Closerとしての開発力の土台ができたのは未踏アドバンストのお陰です。それまでは一つのプロジェクトを複数人で分担して進めることができていませんでしたが、未踏期間中にアドバイスをもらいながら役割分担して進めたことで、今は役割分担して取り組めるようになりました。
未踏アドバンストに参加して一番思い出に残っているのはどんなことですか。

個人的にはすごいレベルの人たちと会って話すという機会を得たことが貴重な経験になりました。特に同期が皆すごい人ばかりでした。「これが未踏か」と思いましたが、同期からたくさんの知見を得ることができました。
最初からロボット系のことばかりしていて、ロボットを動かしたり制御したりするソフトウェア以外のことは知らなかったのですが、未踏アドバンストで知り合った方たちと話すことを通じて技術的な視野が広がりました。
今のCloserの状況を教えてください。

未踏アドバンスト事業が終わった直後に、投資家からシードラウンドで1億円の資金を調達しました。未踏アドバンストの期間に開発していた、小袋を弁当箱などに移動させるロボットの開発は現在でも進めており、今年度末に現場導入を予定しています。ロボット導入に向けて、様々な顧客の工場などを見させていただく機会があるのですが、Closerの強みがほかの領域でも生かせることが分かってきました。
昨年からはもう一つの別のロボット開発が進んでいます。ダンボール箱をつかんで別の場所に運ぶロボットで、未踏アドバンストで磨き上げた小袋をつかんで置く技術を応用したものです。競合製品もありますが物流業界も対象となって市場が大きいため、得意とする小型化と使いやすさで、製品化を進めてきました。
パレットへの積み込み作業であるパレタイズを容易にするロボットという意味を込めて「Palletizy(パレタイジー)」と名付けました。すでに導入実績もあって、現在複数台受注済みです。毎週のように実証実験を行いながら、人の作業をロボットに置き換えるというコンセプトを変えずに、ソフトウェアをアップデートしています。
食品工場ではスペースが限られるために、大型のロボットではコストが見合いませんし、ロボットの専門家もいないので、導入しやすくなければ受け入れてもらえません。今当社のロボットの使いやすさはトップレベルにあると思っています。デモンストレーションを通してそれを理解してもらうようにしています。
今後はどんな展開を考えているのでしょうか。

技術的に高度な製品ができれば海外でも販売することができます。まず国内で実績を積んだ上で将来は海外展開をしていきたいと考えています。経済産業省がシリコンバレーに開設したスタートアップ支援拠点「Japan Innovation Campus」のメンバーにも選ばれ、日頃から展示会で海外の製品を見て、機能を強化したりしています。
Palletizyではファナックのロボットを利用していますが、対象とする汎用ロボットについても広げていきます。展示会で他のロボットメーカーから「当社のロボットに対応する製品を開発してほしい」と声をかけていただくケースも増えてきました。ビジネスの柱ができたので、今後は積極的に横展開にも取り組んでいきます。
Message

未踏アドバンストは技術的な面だけでなく、ビジネス化まで支援してくれます。技術寄りでビジネスとしても面白いことをやっている人にとっては絶好の機会です。私たちも多くのことを吸収できました。この場は疑問があればなんでも聞くことができます。しかも未踏期間が終了した後でも相談できるという特典付きです。
プロフィール
小熊 一矢さん
1999年、新潟県生まれ。長岡工業高等専門学校を卒業後、東北大学大学院工学研究科博士前期課程を修了。現在は同大学院博士後期課程に在籍し、協調ロボットおよびインフラ点検ロボットの研究を進めている。加えて、株式会社Closerに所属し、パレタイズロボや小袋移載ロボの開発に従事している。

技術力のある人に未踏を知ってもらいたいですね。まずとりあえずは応募することです。応募書類を作るときは、審査する人の立場に立って、その人がどこを見て、どう考えるかを意識すると想いが伝わるものになると思います。ロボット系のPMも多いですし、ロボットが作れる人ならなおのこと応募してほしいですね。
プロフィール
樋口 翔太さん
小学生の頃からロボット開発に取り組む。長岡高専に進学し2017年にロボカップジュニアサッカー世界大会で優勝を果たす。2019年には孫正義育英財団に採択。その後、筑波大学大学院に進学し、2021年に株式会社Closerを設立。2024年にForbes 30 UNDER 30 Asia 2024に選出。





